イタチの毛の特徴は?【季節で毛が変化】冬毛と夏毛の違いや、毛色の個体差から見る生存戦略

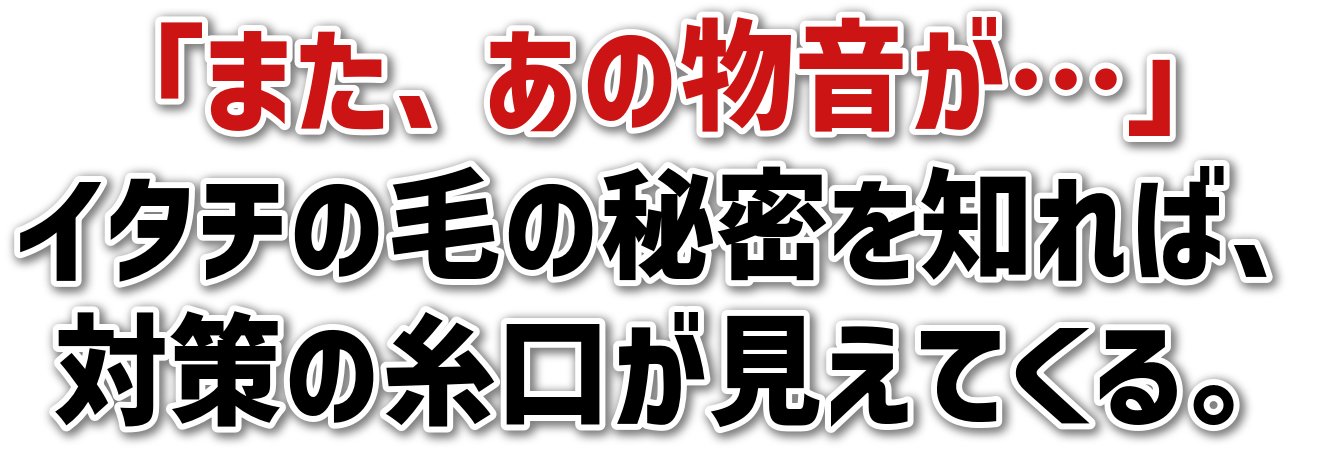
【この記事に書かれてあること】
イタチの毛には驚くべき特徴がたくさんあるんです。- イタチの毛は1平方センチあたり2万本以上の高密度
- 冬毛と夏毛で長さと色が変化し、生態に適応
- 換毛期は年2回の春と秋で、この時期は要注意
- 毛色には茶色から黒褐色まで個体差がある
- イタチの毛の特徴を理解し、効果的な対策を立てる
季節によって変化する毛の長さや色、そして1平方センチメートルあたり2万本以上もの驚異的な密度。
これらの特徴を知ることで、イタチの生態や行動パターンがよく分かるんです。
毛の秘密を解き明かせば、効果的な対策が見えてくるかも。
イタチに困っている方、この記事を読めば、きっと新しい発見があるはずです。
さあ、イタチの毛の不思議な世界を一緒に探検してみましょう!
【もくじ】
イタチの毛の特徴と季節変化

イタチの毛の密度は「驚異の2万本」以上!
イタチの毛は驚くほど密集しています。なんと1平方センチメートルあたり2万本以上もの毛が生えているんです!
「えっ、そんなにたくさん?」と驚かれるかもしれません。
でも、本当なんです。
この驚異的な毛の密度がイタチの生存に大切な役割を果たしています。
まず、この高密度の毛は優れた断熱効果を生み出します。
寒い冬でも体温を逃がさず、暖かく過ごせるんです。
「まるでダウンジャケットを着ているようだね」と言えるでしょう。
さらに、この密集した毛は水をはじく性質も持っています。
イタチが水辺で活動するときに、体が濡れるのを防いでくれるんです。
「ぬるぬる」とした感じではなく、「さらさら」とした手触りなんですよ。
イタチの毛の密度について、もう少し詳しく見てみましょう。
- 赤ちゃんイタチ:生まれたばかりの赤ちゃんイタチは、まだ毛が薄いです。
- 成長期:成長するにつれて、毛の密度が急速に増していきます。
- 成獣:完全に成長したイタチは、最も高い毛の密度を持ちます。
草むらに隠れたとき、その姿がぼやけて見えにくくなるんです。
「まるで忍者のような隠れ身の術だね」と言えるかもしれません。
このように、イタチの毛の高密度は、単なる見た目の特徴ではなく、生存に欠かせない重要な要素なのです。
イタチの生態を理解する上で、この毛の特徴を知ることは非常に大切なんです。
冬毛と夏毛の違い「長さと色」に注目!
イタチの毛は季節によって変化します。冬毛と夏毛では、長さと色に大きな違いがあるんです。
この違いを知ることで、イタチの生態をより深く理解できます。
まず、毛の長さについて見てみましょう。
冬毛は約2〜3センチと長めです。
一方、夏毛は約1〜1.5センチと短めになります。
「なんだか人間の髪の毛みたいだね」と思うかもしれません。
この長さの違いには理由があるんです。
冬は寒さから身を守るため、長い毛が必要になります。
「まるでモコモコのコートを着ているみたい」と言えるでしょう。
夏は暑さをしのぐため、短い毛で体温調節をしやすくしているんです。
次に、毛の色の違いを見てみましょう。
- 冬毛:やや明るい茶色
- 夏毛:濃い茶色
冬は雪や枯れ草に溶け込みやすい明るい色、夏は緑の草むらに隠れやすい濃い色になるんです。
「カメレオンみたいだね」と思うかもしれません。
でも、注意が必要です。
全てのイタチがぴったり同じ色になるわけではありません。
個体差があるので、「うちに来るイタチは違う色だよ」ということもあるかもしれません。
冬毛と夏毛の違いは、イタチの行動にも影響します。
冬は保温性の高い毛で長時間の活動が可能になります。
夏は放熱しやすい毛で、暑い時期でも活発に動き回れるんです。
このように、イタチの毛の季節変化は、単なる見た目の変化ではなく、生存に直結する重要な特徴なんです。
イタチ対策を考える上でも、この季節変化を理解しておくことが大切になりますよ。
換毛期は年2回!「春と秋」が要注意
イタチの毛が生え変わる時期、つまり換毛期は年に2回あります。春と秋がその時期なんです。
この換毛期を知っておくと、イタチの行動予測や対策に役立ちますよ。
春の換毛期は3月から4月頃、秋の換毛期は9月から10月頃に始まります。
「ちょうど服の衣替えの時期と同じだね」と思うかもしれません。
換毛の過程は約2〜3週間かかります。
この間、イタチの様子が少し変わるんです。
具体的にどんな変化があるのか、見てみましょう。
- 皮膚のかゆみ:新しい毛が生えてくるため、体をよくこすりつけます。
- 毛が抜けやすい:古い毛が抜け落ちるので、イタチの毛が見つかりやすくなります。
- 行動が不安定:体調の変化で、普段と違う行動をとることがあります。
でも、イタチの場合は要注意なんです。
なぜなら、この時期のイタチは家の外壁や庭の構造物に体をこすりつける可能性が高くなるからです。
「えっ、うちの壁が傷つくの?」と心配になりますよね。
さらに、換毛期はイタチが新しい巣を探す時期とも重なることがあります。
「もしかして、うちに住み着こうとしているの?」という心配も出てきます。
でも、大丈夫です。
この時期を知っておけば、効果的な対策が立てられます。
例えば:
- 庭に柔らかい布やブラシを置いて、イタチがそこで体をこすれるようにする。
- 家の周りをよく点検し、小さな穴や隙間をふさぐ。
- 換毛期に合わせて、忌避剤の使用を強化する。
春と秋、特に注意して観察してみてくださいね。
毛色の個体差に要注意!「茶色〜黒褐色」まで
イタチの毛色は一定ではありません。茶色から黒褐色まで、かなりの個体差があるんです。
この多様性を知っておくと、イタチの識別や対策に役立ちますよ。
まず、イタチの基本的な毛色の範囲を見てみましょう。
- 明るい茶色
- 中間的な茶色
- 濃い茶色
- 黒褐色
実は、まれに白や薄い灰色の個体も存在するんです。
この毛色の違いは、イタチの生存戦略と深く関係しています。
例えば、暗い森に住むイタチは濃い色の毛を持つ傾向があります。
一方、開けた草原に住むイタチは明るい色の毛を持つことが多いんです。
「カモフラージュみたいだね」と思うでしょう。
その通りなんです。
周囲の環境に合った毛色を持つイタチは、捕食者から身を隠しやすくなります。
つまり、生存率が高くなるんです。
でも、この個体差がイタチ対策を難しくすることもあります。
「茶色いイタチを見たから大丈夫」と思っても、次に来るのは黒褐色のイタチかもしれません。
油断は禁物なんです。
そこで、効果的な対策のポイントをいくつか紹介します。
- 複数の色のイタチがいる可能性を考慮して、幅広い対策を立てる。
- 毛色だけでなく、体の大きさや形、行動パターンなども観察する。
- イタチの毛が見つかったら、その色をメモしておく。
地域のイタチの特徴がわかるかも。
でも、こういった細かな観察が、効果的なイタチ対策につながるんです。
イタチの毛色の個体差を理解することで、より的確な対策が立てられます。
「うちに来るイタチはどんな色かな?」と観察してみるのも面白いかもしれませんね。
イタチの毛は「高品質」!他の小動物と比較
イタチの毛は、実はとても高品質なんです。他の小動物と比べると、その特徴がよくわかります。
この高品質な毛が、イタチの生態にどう影響しているのか、見ていきましょう。
まず、イタチの毛の特徴を簡単にまとめてみます。
- 光沢がある
- 柔らかい
- 密度が高い
- 水をはじく
実際、イタチの毛は昔から毛皮として珍重されてきたんです。
では、他の小動物と比べてみましょう。
例えば、タヌキとの違いを見てみます。
タヌキの毛:やや太くて硬い傾向がある
イタチの毛:細くて柔らかい
「触り心地が全然違いそう」と想像できますね。
この違いは、それぞれの動物の生活環境に適応した結果なんです。
次に、テンとの比較も見てみましょう。
テンの毛:ふわふわとして空気を含みやすい
イタチの毛:光沢があり滑らか
「どっちがあったかいのかな?」と気になりますよね。
実は、どちらも優れた保温性を持っているんです。
ただ、イタチの毛の方が水をはじく性質が強いんです。
この高品質な毛が、イタチの生態にどう影響しているのでしょうか。
- 水辺での活動が得意:水をはじく毛のおかげで、濡れにくく泳ぎも得意。
- 寒さに強い:密度の高い毛が優れた断熱効果を発揮。
- 素早い動き:軽くて柔らかい毛が、スムーズな動きをサポート。
その通りなんです。
この高品質な毛を理解することで、イタチの行動パターンや生態をより深く知ることができます。
例えば、水辺や寒い場所でもイタチが活動できることがわかれば、対策を立てる際の参考になりますよ。
イタチの毛の質の高さは、まさにイタチの生存戦略の要なんです。
この特徴を知っておくことで、より効果的なイタチ対策が可能になるんです。
イタチの毛から見る生態と行動パターン

毛の密度と保温性「水辺での生活」に適応
イタチの毛の高密度と優れた保温性は、水辺での生活に見事に適応しているんです。「えっ、イタチって水辺に住んでるの?」と驚く方もいるかもしれませんね。
実は、イタチは水辺での生活がとっても得意なんです。
その秘密は、驚くほど密集した毛にあるんです。
イタチの毛は、1平方センチメートルあたり約2万から3万本もあるんですよ。
「もふもふ」どころじゃないですね。
まるで超高級のファーコートを着ているようなものです。
この高密度の毛には、すごい特徴があります。
- 優れた断熱効果:体温を逃がさず、寒い水中でも体を温かく保てる
- 高い防水性:水をはじき、体が濡れにくい
- 浮力の向上:水に浮きやすくなる
「まるで小さな潜水服を着ているみたい!」と言えるでしょう。
水辺での生活に適応したイタチの行動を見てみましょう。
- 泳ぎが得意:最大で500メートル以上も泳げちゃうんです
- 潜水も上手:30秒以上も潜れるんですよ
- 魚や水生昆虫を捕まえる:水中での狩りが上手なんです
でも、この特徴は私たちにとって要注意です。
イタチは水路や排水溝を通じて家に侵入してくることもあるんです。
「えっ、そんなところから入ってくるの?」と驚くかもしれません。
だから、家の周りの水辺環境にも注意が必要です。
排水溝や水路の入り口に細かい網を付けたり、庭の池にはフタをしたりするのが効果的です。
イタチの毛の特徴を知ることで、その生態がよくわかりますね。
水辺での生活に適応したイタチの能力を理解すれば、より効果的な対策が立てられるんです。
換毛期と活動量の関係「不安定になる時期」に注意
イタチの換毛期には、その活動量や行動が不安定になるんです。この時期を知っておくと、イタチ対策に大いに役立ちます。
まず、イタチの換毛期はいつ頃なのか、おさらいしておきましょう。
- 春の換毛期:3月から4月頃
- 秋の換毛期:9月から10月頃
さて、この換毛期、イタチにとってはちょっと大変な時期なんです。
「どんな風に大変なの?」と思いますよね。
具体的に見ていきましょう。
- 皮膚のかゆみ:新しい毛が生えてくるため、体がかゆくなります
- 体温調節の不安定:毛が抜け替わる過程で、体温調節がうまくいかなくなることも
- エネルギー消費の増加:新しい毛を生やすのにエネルギーを使います
「ごりごり」と体をこすりつける行動が増えたり、「そわそわ」と落ち着きがなくなったりします。
まるで「むずむず」する足のレストレスレッグス症候群のような感じかもしれません。
この時期、イタチは次のような行動をとりがちです。
- 家の外壁や庭の構造物に体をこすりつける
- 新しい巣や隠れ場所を探し回る
- 普段より活発に動き回る
だからこそ、この時期は特に注意が必要なんです。
では、どんな対策が効果的でしょうか?
- 家の周りをこまめに点検し、小さな穴や隙間をふさぐ
- 庭に柔らかい布やブラシを置いて、イタチが家の外壁ではなくそこでかゆみを解消できるようにする
- 忌避剤の使用を強化する
春と秋、特に気をつけて観察してみてくださいね。
「あ、今がイタチの換毛期かも」と気づけるようになれば、イタチ対策の達人です!
毛色と生存率「環境に適した個体」が有利に
イタチの毛色は、その生存率に大きく影響するんです。環境に適した毛色を持つ個体が、生き残りやすいんです。
「え?毛の色で生き残れるかどうか変わっちゃうの?」と驚く方もいるでしょう。
実は、自然界ではとても重要なんです。
まず、イタチの毛色にはどんな種類があるのか、おさらいしてみましょう。
- 明るい茶色
- 濃い茶色
- 黒褐色
- まれに白や薄い灰色
この多様な毛色は、イタチの生存戦略と深く関係しているんです。
例えば:
- 明るい茶色の個体:草原や麦畑などの明るい環境に適応
- 濃い茶色や黒褐色の個体:森林や茂みなどの暗い環境に適応
- 白や薄い灰色の個体:雪山や岩場などの環境に適応
環境に溶け込むことで、捕食者から身を守りやすくなるんです。
では、環境に適した毛色を持つ個体が有利になる理由を、もう少し詳しく見てみましょう。
- 捕食者に見つかりにくい:身を隠しやすいので、狙われにくくなります
- 獲物に気づかれにくい:逆に、イタチが獲物を狩るときにも有利です
- 体温調節に有利:環境に合った色は、日光の吸収や反射にも影響します
でも、ここで注意が必要です。
環境が変わると、有利だった毛色が不利になることもあるんです。
例えば、森林伐採で明るい環境になると、濃い色のイタチが不利になってしまいます。
この特徴は、イタチ対策にも活かせます。
例えば:
- 庭や家の周りの環境を、イタチが隠れにくい色調にする
- イタチの毛色に合わせた忌避剤や罠の色を選ぶ
- 夜間照明を工夫して、イタチが身を隠しにくい環境を作る
「なるほど、イタチの毛色を見れば、どんな環境から来たのかわかるんだね」と、新しい発見があったのではないでしょうか。
冬毛vs夏毛「季節による行動範囲」の違い
イタチの冬毛と夏毛の違いは、その行動範囲に大きな影響を与えるんです。季節によって、イタチの活動エリアが変わってくるんです。
「えっ、毛が変わるだけで行動も変わるの?」と思う方もいるでしょう。
実は、とても深い関係があるんです。
まず、冬毛と夏毛の特徴をおさらいしましょう。
- 冬毛:長くて密度が高い、やや明るい茶色
- 夏毛:短くて密度が低い、濃い茶色
この違いが、イタチの行動範囲にどう影響するのか、具体的に見ていきましょう。
- 冬の行動範囲:
- 広範囲に活動可能
- 寒冷地や雪山でも活動できる
- 水辺での活動時間が長い
- 夏の行動範囲:
- 比較的狭い範囲で活動
- 日陰や涼しい場所を好む
- 水辺での活動は短時間に
冬毛は保温性が高いので、イタチは寒い環境でも長時間活動できます。
「ぬくぬく」と暖かいコートを着ているようなものですね。
だから、冬は広い範囲を移動しても平気なんです。
一方、夏毛は放熱性が高いので、暑さを避けやすくなります。
でも、直射日光や高温には弱くなるので、活動範囲が限られてきます。
「はぁはぁ」と暑がっている犬を想像してみてください。
この季節による行動範囲の違いは、イタチ対策にも大きく関わってきます。
- 冬の対策:広範囲に注意を払い、家の周りだけでなく、近隣の自然環境にも目を向ける
- 夏の対策:家の周りの日陰や涼しい場所、水辺に特に注意を払う
夏なら「エアコンの室外機の影とか、軒下が危ないかも」と注意します。
このように、イタチの毛の季節変化を理解すれば、その行動範囲も予測しやすくなります。
「なるほど、季節によって警戒するポイントを変えればいいんだね」と、新しい視点が得られたのではないでしょうか。
イタチの毛を利用した効果的な対策方法

換毛期に合わせた「柔らかい布」の設置で被害軽減
イタチの換毛期に合わせて柔らかい布を設置すると、家屋への被害を軽減できるんです。これ、意外と効果的な対策なんですよ。
「え?布を置くだけでいいの?」と思われるかもしれませんね。
実は、イタチの習性をうまく利用した賢い方法なんです。
イタチの換毛期は年に2回、春(3月から4月頃)と秋(9月から10月頃)にやってきます。
この時期、イタチはかゆみを感じて体をこすりたくなるんです。
「むずむず」「かゆかゆ」って感じでしょうか。
そこで登場するのが、柔らかい布やブラシ。
これらを庭や家の周りに設置すると、イタチはそこで体をこすりつけるようになるんです。
「ああ、気持ちいい〜」ってイタチも大喜びかも。
この方法には、いくつかのメリットがあります。
- 家の外壁や庭の構造物への被害を軽減できる
- イタチの行動範囲を把握しやすくなる
- 脱落した毛を集めやすくなり、清掃が楽になる
例えば:
- 庭の隅っこ
- 木の根元
- フェンスの下
- 物置の周り
「ふわふわ」した感触がイタチにも気持ちよさそうですね。
ただし、注意点もあります。
布は定期的に洗濯や交換をしましょう。
放置すると、かえってイタチを引き寄せてしまう可能性があるんです。
「せっかく対策したのに逆効果?」なんてことにならないように気をつけてくださいね。
この方法を試してみると、「あれ?家の壁にイタチの引っかき傷が減った!」なんて嬉しい発見があるかもしれません。
イタチの習性を知って、上手に対策。
それが被害軽減の近道なんです。
毛の色に合わせた「外壁ペイント」で侵入抑制
イタチの毛の色に合わせて外壁をペイントすると、なんと侵入を抑制できるんです。これ、意外と知られていない裏ワザなんですよ。
「えっ?壁の色を変えるだけでイタチが来なくなるの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、イタチの習性をうまく利用した方法なんです。
イタチは、自分の体の色と似た環境を好む傾向があります。
それは身を隠すのに都合がいいからなんです。
でも、逆に言えば、自分の体の色と違う環境は避けたがるんですね。
ここで重要なのが、イタチの毛色です。
一般的なイタチの毛色は:
- 明るい茶色
- 濃い茶色
- 黒褐色
例えば:
- 薄い灰色や白っぽい色の外壁:濃い色のイタチを寄せ付けにくい
- 明るい黄色やクリーム色の外壁:黒褐色のイタチを遠ざける
- 青みがかった色の外壁:茶色系のイタチにとって不自然な環境に
ただし、注意点もあります。
周囲の景観を著しく損なうような派手な色は避けましょう。
ご近所トラブルの元になりかねません。
「イタチは来なくなったけど、隣の人と気まずくなっちゃった…」なんて悲しいことにならないように気をつけてくださいね。
この方法のいいところは、一度ペイントすれば長期的に効果が続くこと。
「塗って安心、イタチバイバイ」というわけです。
もちろん、ペイントだけでなく、他の対策も組み合わせるとさらに効果的です。
例えば、前回お話した柔らかい布の設置と組み合わせれば、「イタチさん、ここには来ないで、あっちで毛づくろいしてね」って感じで誘導できるかもしれません。
イタチの習性を知って、賢く対策。
それが快適な住環境への近道なんです。
季節別「香り」の使い分けで効果的な忌避
イタチの毛が季節で変化するように、忌避に使う香りも季節で使い分けると効果的なんです。これ、意外と知られていない対策方法なんですよ。
「えっ?季節によって香りを変えるの?」と思われるかもしれませんね。
実は、イタチの生態をよく理解した上での戦略なんです。
イタチの毛は季節によって変化します。
冬毛は長くて密度が高く、夏毛は短くて密度が低いんです。
この違いは、イタチの嗅覚にも影響を与えるんですよ。
そこで、季節別の香り対策を見てみましょう:
- 冬(冬毛の時期):強い香りの忌避剤が効果的
- 夏(夏毛の時期):軽い香りの忌避剤でも十分
- 春・秋(換毛期):中程度の香りで様子を見る
- 冬におすすめの強い香り:
- ペパーミント
- ユーカリ
- シナモン
- 夏におすすめの軽い香り:
- ラベンダー
- レモングラス
- シトロネラ
この方法のポイントは、イタチの鼻の敏感さに合わせて香りの強さを調整すること。
冬は毛が密集しているので強い香りが必要ですが、夏は毛が薄いので軽い香りでもイタチには十分効果があるんです。
ただし、注意点もあります。
人間にとっても強すぎる香りは避けましょう。
「イタチは来なくなったけど、自分も家にいられない!」なんて本末転倒にならないように気をつけてくださいね。
この季節別香り戦略、実は一石二鳥なんです。
イタチ対策になるだけでなく、季節の移り変わりを香りで楽しめるんですよ。
「あ、もうユーカリの香りの季節か。冬が近いな」なんて、季節を感じる新しい楽しみ方にもなるかもしれません。
イタチの生態を理解して、季節に合わせた対策。
それが効果的な忌避への近道なんです。
香りで季節を楽しみながら、イタチともうまく付き合っていきましょう。
静電気を利用した「不快な環境作り」で撃退
イタチの毛が静電気を帯びやすい特性を利用して、不快な環境を作り出すことで効果的に撃退できるんです。これ、ちょっと変わった対策方法なんですよ。
「え?静電気でイタチを追い払えるの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、イタチの毛の特徴をうまく利用した科学的な方法なんです。
イタチの毛は非常に密集していて、静電気を帯びやすい特性があります。
この特性を逆手に取って、イタチにとって不快な環境を作り出すんです。
具体的な方法をいくつか紹介しましょう:
- 出入り口付近に静電気を発生させる装置を設置する
- 侵入経路に金属製の網を張る
- 庭や家の周りに帯電しやすい素材を配置する
- イタチが接触したときに軽い静電気ショックを感じる
- 毛が逆立って不快感を覚える
- 静電気の存在を察知して近づかなくなる
この方法のポイントは、イタチに危害を加えるのではなく、ただ不快に感じさせること。
痛みを与えるわけではないので、人道的な対策方法と言えるでしょう。
ただし、注意点もあります。
雨の日や湿度が高い日は効果が落ちる可能性があります。
「せっかく設置したのに、雨が降ったら意味ないの?」って心配になるかもしれませんが、そんなときは他の対策と組み合わせるのがおすすめです。
面白いのは、この方法を使うと、静電気でイタチの毛がふわふわに逆立つ様子が見られるかもしれないこと。
「まるでイタチのパーマみたい!」なんて、ちょっとおかしな光景に出会えるかもしれません。
イタチの特性を理解して、ちょっと変わった方法で対策。
それが新しい撃退法の発見につながるんです。
静電気を味方につけて、イタチとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。
毛の密度を考慮した「5ミリ以下の隙間」封鎖
イタチの毛の密度を考慮して、5ミリ以下の隙間を全て封鎖することで、効果的に侵入を防ぐことができるんです。これ、地道だけど確実な対策方法なんですよ。
「えっ?そんな小さな隙間まで?」と思われるかもしれませんね。
でも、イタチの体の特徴を知ると、納得がいくはずです。
イタチの毛は驚くほど密集しています。
1平方センチメートルあたり約2万から3万本もの毛が生えているんです。
この密度の高さが、イタチの小さな隙間への侵入を可能にしているんです。
では、具体的にどんな場所を封鎖すればいいのでしょうか?
- 家の外壁や基礎部分の小さなひび割れ
- 屋根裏や床下の換気口
- 窓や扉の隙間
- 配管や電線の通り道
- 金属製のメッシュシートを使用
- 専用のフォームスプレーで隙間を埋める
- シリコンコーキングで細かい隙間を塞ぐ
- 木材や金属プレートで大きめの穴をカバー
この方法のポイントは、徹底的に細かい部分まで気を配ること。
「ここくらいなら大丈夫かな」なんて油断は禁物です。
イタチは本当に小さな隙間から入り込んでくるんですから。
ただし、注意点もあります。
家の通気性を妨げないように気をつけましょう。
「イタチは入れなくなったけど、家の中がむしむしする…」なんてことにならないように、適度な換気ができる構造を保つことが大切です。
面白いのは、この作業をしていると家のいろんな場所を細かくチェックすることになるので、思わぬ家の不具合を発見できるかもしれないこと。
「イタチ対策のつもりが、家のメンテナンスになっちゃった!」なんて面白いのは、この作業をしていると家のいろんな場所を細かくチェックすることになるので、思わぬ家の不具合を発見できるかもしれないこと。
「イタチ対策のつもりが、家のメンテナンスになっちゃった!」なんて嬉しい誤算もあるかもしれません。
イタチの毛の特徴を理解して、細部まで気を配る。
それが確実な侵入防止への近道なんです。
5ミリ以下の隙間を封鎖して、イタチとの上手な距離感を保ちましょう。
家全体の健康チェックにもなる、一石二鳥の対策方法かもしれませんね。