イタチは何を食べる?【小動物が主食】季節で変化する食性と、1日の採餌回数の驚きの事実

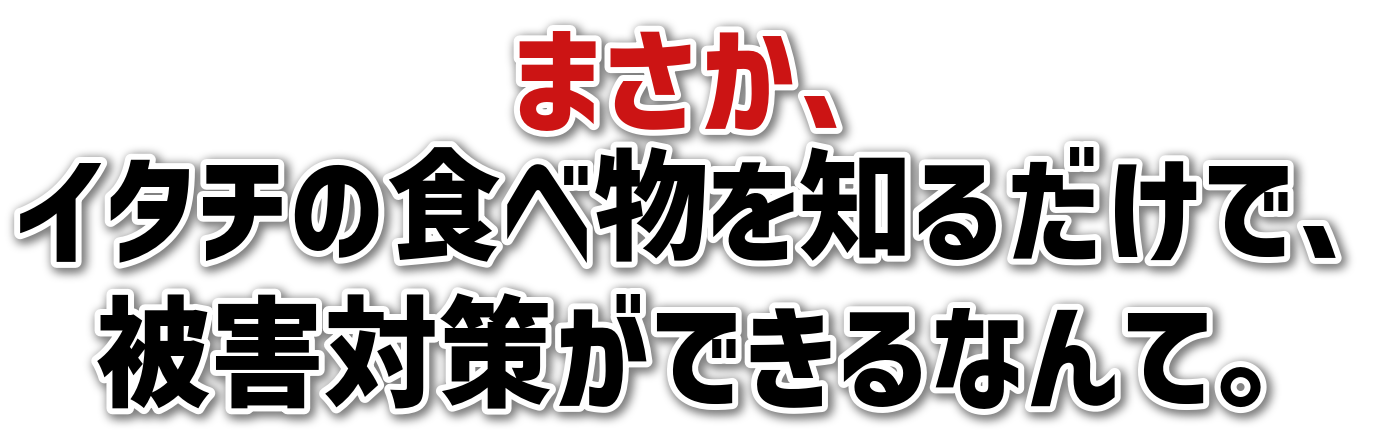
【この記事に書かれてあること】
イタチの食性について知っていますか?- イタチは小型哺乳類や昆虫を主に捕食する肉食動物
- 季節によって食性が変化し、環境に適応する柔軟性
- イタチの俊敏な動きと鋭い感覚が高い捕食効率を実現
- 夜行性で、主に夜間に活発な採餌活動を行う
- イタチの食性を理解することで効果的な被害対策が可能に
実は、イタチの食べ物を理解することが、効果的な被害対策の第一歩なんです。
小さな体に秘められた驚きの食欲と、季節によって変化する食性。
そして、イタチの俊敏な狩猟能力は、まるで忍者のよう!
「ガサガサ」「ピョンピョン」と庭を駆け回るイタチの姿を想像してみてください。
この記事では、イタチの食生活の秘密に迫り、その知識を活かした賢い対策法をご紹介します。
イタチとの上手な付き合い方、一緒に考えてみませんか?
【もくじ】
イタチは何を食べる?小動物が主食の肉食動物

イタチの主食は「ネズミ類」!体重の20%を毎日摂取
イタチの主食はネズミ類です。毎日、自身の体重の約20%もの餌を食べる大食漢なんです。
「イタチってどんな食べ物が好きなの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実はイタチは、ネズミを中心とした小動物が大好物なんです。
特に好んで食べるのは以下のような動物たちです。
- ハツカネズミ
- ドブネズミ
- クマネズミ
- モグラ
- リス
ネズミが「キーッ」と鳴く間もなく、イタチの鋭い歯で仕留められてしまうんです。
イタチの食欲は旺盛で、なんと1日に自身の体重の約20%もの餌を食べるそうです。
「えっ、そんなに食べるの!?」と驚きますよね。
例えば、体重300グラムのイタチなら、1日に60グラムもの餌を食べることになります。
これは人間に換算すると、体重60キロの人が毎日12キロの食事をするようなものです。
イタチがこれほど多くの餌を必要とする理由は、高い代謝率と活発な活動にあります。
小さな体で素早く動き回るイタチは、常にエネルギーを消費しているんです。
「食べても食べても痩せない」なんて羨ましい体質かもしれませんね。
このようにイタチは、ネズミ類を主食とする肉食動物なんです。
その旺盛な食欲は、彼らの生態系での役割を支える重要な要素になっているんです。
イタチの食性は「季節で変化」!夏は昆虫類も大好物
イタチの食性は季節によって変化します。夏になると昆虫類も大好物になるんです。
「イタチって一年中同じものを食べているの?」なんて思ったことはありませんか?
実はイタチの食事メニューは、季節によってがらりと変わるんです。
春から夏にかけて、イタチの食卓には次のようなおかずが並びます。
- カエル
- トカゲ
- 小鳥の卵
- コオロギ
- バッタ
昆虫は栄養価が高く、イタチにとって格好のおやつになるんです。
一方、秋から冬にかけては、こんな食べ物が人気です。
- ネズミ類
- モグラ
- 小鳥
ネズミ一匹で、イタチの1日分のエネルギー源になることもあるそうです。
イタチの食性が季節で変化する理由は、環境への適応能力の高さにあります。
「その時期に手に入りやすい餌を効率よく食べる」という戦略が、イタチの生存を支えているんです。
さらに面白いことに、イタチは時々果実も食べるんです。
「えっ、肉食動物なのに?」と驚きますよね。
これは栄養バランスを整えるためだと考えられています。
このように、イタチの食性は季節とともに変化し、その時々で最適な栄養摂取を行っているんです。
自然界での巧みな生存戦略が見えてきますね。
イタチvs他の小型哺乳類!「食物連鎖の頂点」に君臨
イタチは小型哺乳類の中で食物連鎖の頂点に立っています。その強さの秘密は、優れた狩猟能力にあるんです。
「イタチってそんなに強いの?」と思う人もいるかもしれません。
でも、イタチの狩猟能力を知ると、きっと驚くはずです。
イタチは次のような特徴を持っています。
- 素早い動き
- 鋭い歯と爪
- 優れた嗅覚
- 高い知能
- 柔軟な体
例えば、ネズミの巣穴を見つけると、細長い体を活かして中に潜り込みます。
「ズルズル」と音を立てながら進むイタチに、ネズミは逃げ場を失ってしまうんです。
イタチの狩猟能力は、他の小型哺乳類と比べても群を抜いています。
例えば:
- ウサギよりも俊敏
- リスよりも木登りが上手
- モグラよりも地中での動きが素早い
イタチが食物連鎖の頂点に立つ理由は、この優れた狩猟能力だけではありません。
実は、イタチには天敵が少ないんです。
大型の猛禽類や、たまにキツネに襲われることはありますが、同じサイズの動物の中では最強と言えるでしょう。
このようにイタチは、小型哺乳類の世界で「食う側」として君臨しているんです。
その生態を知ると、小さな体に秘められた驚くべき能力に感心してしまいますね。
イタチの食性が「生態系に与える影響」に注目!
イタチの食性は、生態系に大きな影響を与えています。特に、ネズミ類の個体数調整に重要な役割を果たしているんです。
「イタチが食べ物を食べるだけで、そんなに影響があるの?」と思う人もいるかもしれません。
でも、実はイタチの食性は生態系のバランスを保つ重要な要素なんです。
イタチの食性が生態系に与える影響は、主に以下の3つです。
- ネズミ類の個体数調整
- 害虫の抑制
- 他の捕食者との競合
イタチ1匹が1年間に食べるネズミの数は、なんと2,000匹以上にもなるそうです。
「えっ、そんなにたくさん!?」と驚きますよね。
この旺盛な食欲のおかげで、ネズミの個体数が急激に増えることを防いでいるんです。
ネズミが増えすぎると、農作物への被害や感染症の拡大などの問題が起きかねません。
イタチは、そんな問題を未然に防ぐ自然の調整役として活躍しているんです。
また、イタチは害虫も食べるので、農業にも間接的に貢献しています。
「ガサガサ」と畑を歩くイタチは、実は農家の味方なんです。
一方で、イタチの存在は他の捕食者にも影響を与えます。
例えば、フクロウやタカなどの猛禽類と餌を巡って競合することもあるんです。
これは生態系のバランスを保つ上で重要な相互作用になっています。
このように、イタチの食性は生態系全体に波及する影響を持っているんです。
小さな体ながら、自然界で重要な役割を果たしているイタチ。
その存在の大切さが分かりますね。
イタチの狩猟方法と採餌行動の特徴

イタチの「俊敏な動き」で獲物を仕留める!驚異の捕食力
イタチは驚くほど俊敏な動きで獲物を捕まえます。その素早さと正確さは、まるで忍者のよう!
「イタチってどうやって獲物を捕まえるの?」と思ったことはありませんか?
実は、イタチの狩猟方法はとてもユニークなんです。
イタチの捕食力の秘密は、以下の特徴にあります。
- 細長い体を活かした素早い動き
- 鋭い反射神経
- 驚くほどの柔軟性
- 強力な顎と鋭い歯
「ビュン!」という音が聞こえそうなほどの速さです。
その動きは、まるでジグザグの稲妻のよう。
獲物が逃げる暇もありません。
イタチの体は、獲物を追いかけるのに最適な形をしています。
細長い体は、狭い場所でも自在に動けるんです。
「ヌルッ」と草むらや岩の隙間をすり抜けて、獲物に忍び寄ります。
そして、獲物に近づくとイタチは一気に飛びかかります。
その瞬間、イタチの体は弓なりに曲がり、獲物の首筋めがけて鋭い歯を突き立てます。
「ガブッ!」という音とともに、あっという間に獲物を仕留めてしまうんです。
この俊敏な動きと正確な攻撃のおかげで、イタチの捕食成功率はとても高いんです。
例えば、ネズミを追いかける場合、80%以上の確率で捕まえることができるそうです。
イタチの狩猟能力を知ると、小さな体に秘められた驚異的な力に感心してしまいますね。
自然界の中で、イタチが生き抜いてきた理由がよくわかります。
イタチは「木登りも水泳も得意」!多彩な狩猟スキル
イタチは陸上だけでなく、木の上でも水中でも自在に動き回る多才な狩人なんです。その多彩なスキルは、まるでスーパーヒーローのよう!
「イタチって木に登れるの?泳げるの?」と疑問に思う人も多いかもしれません。
実は、イタチは驚くほど器用で、さまざまな環境で狩りをすることができるんです。
イタチの多彩な狩猟スキルには、次のようなものがあります。
- 木登り名人:5メートル以上の高さまで登れる
- 泳ぎの達人:500メートル以上泳ぐことも
- 穴掘りの専門家:地中の獲物も逃がさない
- ジャンプの達人:体長の3倍以上跳べる
その姿は、まるでリスのよう。
木の上にいる小鳥や昆虫も、イタチからは逃げられません。
水中では、イタチはまるでウナギのようにしなやかに泳ぎます。
「スイスイ」と水面を進み、時には潜って魚を追いかけることもあるんです。
川や池の魚たちにとって、イタチは恐ろしい天敵になっているわけです。
地中では、イタチは前足で素早く土を掘り進みます。
「ガリガリ」という音とともに、モグラやネズミの巣穴に侵入していきます。
地下の世界でも、イタチの狩りは止まりません。
そして、地上では驚異的なジャンプ力を発揮します。
体長の3倍以上もの高さや距離を跳ぶことができるんです。
「ビョーン!」と飛び跳ねるイタチの姿は、まるでミニチュアのカンガルーのよう。
このように、イタチは陸、空、水、地中とあらゆる場所で狩りをすることができます。
その多彩なスキルのおかげで、イタチは様々な環境に適応し、生き延びてきたんです。
イタチの生態を知れば知るほど、その驚くべき能力に感心してしまいますね。
イタチの「夜行性」を活かした効率的な採餌戦略とは
イタチは主に夜行性で、夜の闇を味方につけた効率的な採餌戦略を持っています。その戦略は、まるで夜の忍者のようです!
「イタチってどんな時間に活動しているの?」と思ったことはありませんか?
実は、イタチの活動時間の80%以上が夜なんです。
夜行性のイタチは、次のような特徴を活かして効率的に餌を探しています。
- 優れた夜間視力
- 静かな動きで獲物に忍び寄る能力
- 鋭い嗅覚で餌を探知
- 夜行性の獲物が多い時間帯に活動
まるで夜間撮影用のカメラのような目を持っているんです。
「キラリ」と光る目で、真っ暗な中でも獲物を見つけることができます。
また、イタチは夜の静けさを利用して、獲物に忍び寄ります。
「シーン」とした夜の中、イタチはまるで影のように音もなく動き回るんです。
獲物が気づいたときには、もう遅いというわけです。
イタチの鼻は非常に敏感で、暗闇の中でも餌のありかを嗅ぎ分けることができます。
「クンクン」と鼻を動かしながら、獲物の匂いを追いかけていくんです。
さらに、イタチの主な獲物であるネズミやモグラなども夜行性。
つまり、イタチは獲物が最も活発に動き回っている時間帯に狩りをしているんです。
これは、まるで魚が一番釣れる時間を狙って釣りに行くようなものです。
このような夜行性の特徴を活かした採餌戦略のおかげで、イタチは効率よく餌を確保することができるんです。
昼間はほとんど見かけないイタチですが、夜になると驚くほど活発に活動しているんですね。
イタチの夜の世界での活躍を想像すると、小さな体に秘められた驚くべき能力に感心してしまいます。
自然界の中で、イタチがいかに巧みに生き抜いているかがよくわかりますね。
イタチの「臭覚と聴覚」が鋭い!獲物発見のカギ
イタチは驚くほど鋭い臭覚と聴覚を持っており、これらが獲物発見の重要なカギとなっています。まるで超能力を持っているかのようです!
「イタチはどうやって獲物を見つけるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、イタチの優れた感覚が大きな役割を果たしているんです。
イタチの臭覚と聴覚の特徴は次のとおりです。
- 人間の100倍以上の嗅覚能力
- 超高周波音まで聞こえる聴覚
- 地中の獲物も感知できる能力
- 獲物の動きを予測する能力
人間には感じ取れないような微かな匂いも、イタチにはバッチリ分かるんです。
「クンクン」と鼻を動かしながら、獲物の匂いを追いかけていきます。
耳も負けていません。
イタチは人間には聞こえない高い周波数の音まで聞き取ることができます。
例えば、地中にいるモグラが動く音や、遠くにいるネズミの鳴き声も聞こえてしまうんです。
「ピコピコ」という小さな音も、イタチには大きな手がかりになります。
さらに驚くべきことに、イタチは地面の振動を感じ取ることもできます。
これは、まるで地震を予知する能力のようです。
地中にいる獲物の動きも、イタチには「ドンドン」と伝わってくるんです。
こうした優れた感覚を組み合わせて、イタチは獲物の位置や動きを正確に予測します。
獲物が逃げ出す前に、その行動を読み取ってしまうんです。
「あっち!」「こっち!」と、まるで獲物の心が読めているかのようです。
このように、イタチの鋭い臭覚と聴覚は、効率的な狩りを可能にしています。
小さな体に秘められた驚くべき能力に、思わず感心してしまいますね。
自然界でイタチが生き抜いてきた理由が、よくわかります。
イタチvs他の捕食者!「捕食効率の比較」で見えてくるもの
イタチの捕食効率は、他の小型捕食者と比べてもかなり高いんです。その驚くべき能力は、まるで自然界のスーパースターのよう!
「イタチって他の動物と比べてどのくらい上手に獲物を捕まえられるの?」と思ったことはありませんか?
実は、イタチの捕食効率は驚くほど高いんです。
他の捕食者と比較すると、次のような特徴が見えてきます。
- ネコよりもネズミ捕りが上手
- タヌキよりも昆虫の捕食が得意
- カラスよりも鳥の巣を荒らすのが上手
- キツネよりも小動物の捕獲成功率が高い
でも、実はイタチの方がネズミ捕りの名人なんです。
イタチは1日に10匹以上のネズミを捕まえることができるそうです。
「ガバッ」「ガバッ」とネズミを次々と捕まえていくイタチの姿は、まるでネズミ捕りの機械のよう。
昆虫の捕食でも、イタチは他の動物を上回ります。
タヌキも昆虫を食べますが、イタチの方がより俊敏で小回りが利くため、飛ぶ昆虫も逃がしません。
「ピョン」「パクッ」と、空中で昆虫を捕まえる姿は、まるでアクロバット選手のようです。
鳥の巣荒らしでも、イタチはカラスよりも効率的です。
細長い体を活かして、カラスが入れないような狭い隙間にも侵入できるんです。
「ヌルッ」と木の穴に潜り込み、卵や雛を捕まえてしまいます。
全体的な小動物の捕獲成功率で見ても、イタチはキツネを上回ります。
イタチの方が小型で俊敏なため、小さな獲物を捕まえるのに適しているんです。
キツネが「ガサガサ」と音を立てて近づく頃には、イタチはもう獲物を捕まえているかもしれません。
このように、イタチは他の捕食者と比べても非常に高い捕食効率を誇っています。
小さな体に秘められた驚くべき能力に、思わず感心してしまいますね。
自然界でイタチが重要な役割を果たしている理由が、よくわかります。
イタチの食性を理解して効果的な被害対策を

イタチの「好物を知る」ことが対策の第一歩!
イタチの好物を知ることは、効果的な被害対策の第一歩です。イタチの食べ物の好みを理解すれば、被害を防ぐヒントが見えてきます。
「イタチって何が好きなの?」と思ったことはありませんか?
実は、イタチの食べ物の好みを知ることで、多くの対策のヒントが得られるんです。
イタチが特に好む食べ物には、次のようなものがあります。
- ネズミ類(ハツカネズミ、ドブネズミなど)
- 小鳥や鳥の卵
- カエルやトカゲなどの両生類・爬虫類
- 昆虫類(コオロギ、バッタなど)
- 小魚や水生昆虫
「ガサガサ」と物音がしたら、イタチが餌を探している証拠かもしれません。
イタチの好物を知ることで、次のような対策が考えられます。
- ネズミ対策を徹底する(餌を減らす)
- 鳥の巣箱や餌台を家から離して設置する
- 庭の池や水辺の管理を行う(カエルや小魚を守る)
- 屋外での食事や食べ物の放置を避ける
「イタチよけのためにネズミ対策?」と思うかもしれませんが、実はとても効果的な方法なんです。
また、イタチは果物も時々食べます。
熟した果実を放置しておくと、イタチを引き寄せてしまう可能性があるんです。
「まさか果物がイタチを呼んでいるなんて!」と驚くかもしれません。
このように、イタチの好物を知ることで、私たちの生活習慣を少し見直すだけで、イタチの被害を大きく減らすことができるんです。
イタチの食べ物の好みを理解することは、効果的な対策の第一歩なんです。
イタチが嫌う「香りや音」を活用した追い払い術
イタチが嫌う香りや音を上手に活用すれば、効果的にイタチを追い払うことができます。自然な方法でイタチを寄せ付けない環境づくりが可能になるんです。
「イタチを追い払う良い方法はないかな?」と悩んでいる人も多いはず。
実は、イタチの嫌いな香りや音を利用すれば、穏やかにイタチを遠ざけることができるんです。
イタチが特に苦手とする香りや音には、次のようなものがあります。
- ハッカ油やペパーミントの香り
- 柑橘系の香り(レモン、オレンジなど)
- ラベンダーの香り
- 高周波音(人間には聞こえにくい音)
- 突発的な光や音
例えば、ハッカ油を水で薄めて庭にスプレーすると、イタチは「プンプン」とその香りを嫌がって近づかなくなるんです。
音を使った対策も効果的です。
高周波音を発生する装置を設置すると、イタチは「キーン」という音が苦手で近寄りにくくなります。
人間には聞こえにくい音なので、私たちの生活に支障をきたすことはありません。
さらに、突発的な光や音を利用する方法もあります。
動きを感知して点灯する照明を設置すると、イタチが近づいたときに「パッ」と明るくなって驚かせることができます。
これらの方法を組み合わせて使うのもおすすめです。
例えば、次のような組み合わせが効果的です。
- 庭にハッカ油スプレーを噴霧 + 高周波音発生装置の設置
- ラベンダーの植栽 + 動き感知式照明の設置
- 柑橘系の精油を使った芳香剤 + 不規則に鳴る風鈴
自然な方法でイタチを遠ざけることができるので、環境にも優しい対策と言えます。
イタチの嫌いな香りや音を活用することで、穏やかにイタチを追い払うことができるんです。
人間にも快適で、イタチにとっては不快な環境づくりが、効果的な追い払い術の秘訣なんです。
イタチの「採餌場所」を特定して重点的に対策を
イタチの採餌場所を特定し、そこに重点的に対策を施すことで、効果的にイタチの被害を防ぐことができます。イタチの行動パターンを知れば、対策の的を絞ることができるんです。
「イタチはどこで食べ物を探しているんだろう?」と思ったことはありませんか?
実は、イタチには好んで餌を探す場所があるんです。
イタチが頻繁に採餌活動を行う場所には、次のようなものがあります。
- 庭の生け垣や茂み
- 物置や倉庫の周辺
- コンポスト(堆肥)置き場
- ゴミ置き場
- 軒下や屋根裏
例えば、生け垣や茂みは「サワサワ」とイタチが身を隠しやすい場所。
ここを整理して見通しを良くすれば、イタチが近づきにくくなります。
物置や倉庫の周辺も要注意です。
ここにネズミが住み着いていると、イタチを引き寄せてしまいます。
「ガタガタ」と物音がしたら、イタチが餌を探している可能性があります。
採餌場所を特定したら、次のような対策を重点的に行いましょう。
- 茂みや生け垣の整理(見通しを良くする)
- 物置周辺の清掃と整理(ネズミの住処をなくす)
- コンポスト置き場の管理(蓋をしっかり閉める)
- ゴミ置き場の清潔維持(生ゴミの管理を徹底)
- 建物の隙間封鎖(5ミリ以下の隙間もふさぐ)
生ゴミをしっかり密閉して保管すれば、イタチを引き寄せる匂いを抑えることができます。
「えっ、ゴミの管理だけでイタチ対策になるの?」と思うかもしれませんが、実はとても重要なポイントなんです。
また、建物の隙間を塞ぐことも大切です。
イタチは驚くほど小さな隙間から侵入できるので、5ミリ以下の隙間も見逃さないようにしましょう。
「こんな小さな隙間から入れるの?」と驚くかもしれませんが、イタチの体は非常に柔軟なんです。
このように、イタチの採餌場所を特定し、そこに重点的に対策を施すことで、効果的にイタチの被害を防ぐことができます。
イタチの行動パターンを知り、的を絞った対策を行うことが、成功の秘訣なんです。
イタチの「食性を利用」した生態系管理の可能性
イタチの食性を理解し、それを利用した生態系管理を行うことで、イタチとの共存を図りつつ、被害を最小限に抑えることができます。イタチの生態系での役割を活かすことが、長期的な解決策につながるんです。
「イタチって生態系にとって悪者なの?」と思う人もいるかもしれません。
でも、実はイタチには重要な役割があるんです。
イタチの食性を利用した生態系管理には、次のようなメリットがあります。
- ネズミなどの小動物の個体数調整
- 害虫の抑制
- 生物多様性の維持
- 農作物被害の間接的な軽減
適度にイタチが生息していれば、ネズミの個体数が爆発的に増えるのを防ぐことができます。
「えっ、イタチがいた方がいいの?」と驚くかもしれませんが、適度な数のイタチは生態系のバランス維持に役立つんです。
イタチの食性を利用した生態系管理の具体的な方法には、次のようなものがあります。
- イタチの生息地を適度に確保する(森林や草地の保全)
- イタチが好む餌動物の生息環境を整える(生物多様性の促進)
- 農地周辺にイタチの生息可能な緩衝地帯を設ける
- 化学農薬の使用を控え、生物的防除を促進する
ここにイタチが生息できる環境を整えることで、農作物への直接的な被害を減らしつつ、害虫やネズミの個体数を抑制することができます。
「イタチを近づけないんじゃなかったの?」と思うかもしれませんが、適度な距離を保つことが大切なんです。
また、化学農薬の使用を控えることも重要です。
農薬の過剰使用は、イタチの餌となる昆虫や小動物を減少させ、結果的にイタチが人家に近づく原因になることがあります。
「ガサガサ」と庭を歩くイタチの姿が減れば、自然と被害も減っていくんです。
このように、イタチの食性を理解し、それを利用した生態系管理を行うことで、イタチとの共存を図りつつ、被害を最小限に抑えることができます。
長期的な視点で見れば、イタチの生態系での役割を活かすことが、持続可能な解決策につながるんです。
イタチと「共存する方法」を考える!被害対策のその先へ
イタチと共存する方法を考えることは、単なる被害対策を超えた、より良い環境づくりにつながります。イタチの存在を完全に排除するのではなく、上手に付き合っていく知恵が求められているんです。
「イタチと共存?そんなの無理じゃない?」と思う人も多いかもしれません。
でも、実はイタチと共存することで、私たちの生活環境も良くなる可能性があるんです。
イタチと共存するメリットには、次のようなものがあります。
- 生態系のバランス維持
- ネズミなどの有害生物の自然な抑制
- 農作物への間接的な保護効果
- 自然観察や環境教育の機会
「ネズミ退治にイタチを利用する?」と驚くかもしれませんが、これは自然界ではよくある関係なんです。
では、具体的にどうやってイタチと共存すればいいのでしょうか。
以下のような方法が考えられます。
- イタチの生息地と人間の生活圏を適度に分ける
- イタチに配慮した庭づくり(隠れ家と開けた空間のバランス)
- 自然な防御策の活用(香りや音を使った緩やかな追い払い)
- 地域ぐるみでイタチとの付き合い方を考える
- イタチの生態や役割について学び、理解を深める
完全に開けた空間ではイタチは警戒してしまいますが、適度な隠れ家があれば安心して行動できます。
「イタチのための庭づくり?」と思うかもしれませんが、これは他の野生動物にとっても良い環境になるんです。
また、地域ぐるみでイタチとの付き合い方を考えることも大切です。
一軒だけでは限界がありますが、近所で協力すれば効果的な対策が可能になります。
「ご近所でイタチ対策?」と驚くかもしれませんが、実は地域の環境改善にもつながる取り組みなんです。
さらに、イタチの生態や役割について学ぶことで、イタチに対する見方が変わるかもしれません。
例えば、イタチが害虫を食べてくれることで、農薬の使用量を減らせる可能性があります。
「イタチが農業の味方?」と思うかもしれませんが、自然の力を利用した農業は今注目されているんです。
このように、イタチと共存する方法を考えることは、単なる被害対策を超えた、より良い環境づくりにつながります。
イタチの存在を完全に排除するのではなく、上手に付き合っていく知恵が、これからの時代には求められているんです。
イタチとの共存は、私たちの生活環境をより豊かにする可能性を秘めているんです。