イタチから畑を守る方法は?【電気柵が最も効果的】設置のコツと3つの補助的対策で被害を激減

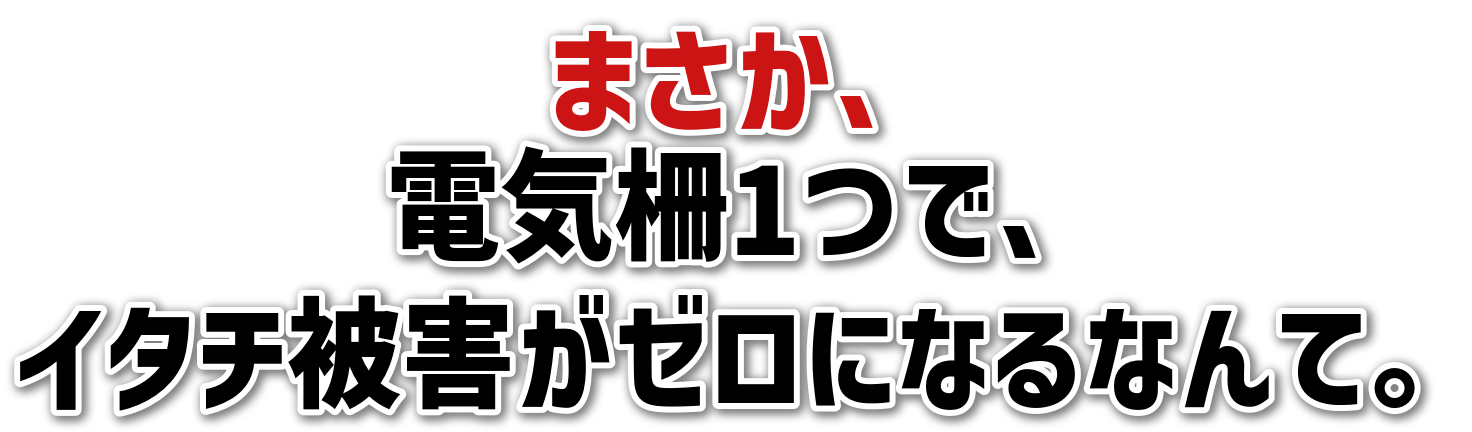
【この記事に書かれてあること】
イタチの被害に悩まされる農家さんや家庭菜園愛好家の皆さん、お困りではありませんか?- イタチによる畑被害の実態と深刻さ
- 電気柵がイタチ対策に最も効果的な理由
- 電気柵の正しい設置方法とメンテナンスのポイント
- 電気柵と他の対策方法の比較と併用効果
- イタチを寄せ付けない5つの意外な裏技
大切に育てた作物が、一晩でむしゃむしゃと食べられてしまう。
そんな悔しい経験をされた方も多いのではないでしょうか。
でも、大丈夫です!
イタチから畑を守る効果的な方法があるんです。
電気柵を中心とした対策と、意外な裏技を組み合わせることで、被害をぐっと減らせるんです。
「よし、これで安心して畑仕事ができる!」そんな日々を取り戻しましょう。
【もくじ】
イタチから畑を守る深刻な被害と対策の必要性

イタチによる畑被害の実態!作物の種類別被害状況
イタチによる畑被害は想像以上に深刻です。作物の種類によって被害の特徴が異なるんです。
まず、果物への被害が目立ちます。
「あら、せっかく育てたイチゴがなくなっちゃった!」なんて経験ありませんか?
イタチは甘い果実が大好物。
特にイチゴ、トマト、メロンなどが狙われやすいんです。
野菜も被害に遭います。
トウモロコシやカボチャは、イタチにとって格好のごちそう。
「せっかく大きくなったトウモロコシが、一晩でむしゃむしゃやられちゃった…」なんて悲劇も珍しくありません。
被害を受けやすい作物の特徴は3つあります。
- 地面に近い位置にある果実
- 柔らかくて香りの強い作物
- 熟した作物
まるで「いらっしゃいませ〜」と言っているようなものです。
季節によっても被害の程度が変わります。
春から秋にかけて被害が増え、特に夏から初秋の収穫期がピーク。
冬は餌が少なくなるため、貯蔵している作物も狙われやすくなるんです。
イタチの被害は見た目だけでなく、収穫量の減少にも直結します。
「今年は収穫が少なくて、家族や近所におすそ分けできないなぁ…」なんて寂しい思いをしたくありませんよね。
イタチ対策は、豊かな収穫を守るための重要な取り組みなのです。
イタチの侵入経路「5つの要注意ポイント」を確認
イタチは意外なところから畑に侵入してきます。侵入経路を知ることが、効果的な対策の第一歩。
要注意ポイントを5つ紹介します。
まず、フェンスの隙間です。
「うちのフェンスは頑丈だから大丈夫」なんて油断は禁物。
イタチは驚くほど小さな隙間をすり抜けられるんです。
わずか3センチの隙間があれば、すいすい入ってきちゃいます。
次に、地面の穴。
イタチは穴掘りの名人。
畑の周りに小さな穴を見つけたら要注意です。
「あれ?この穴、昨日はなかったような…」そう思ったら、イタチの仕業かもしれません。
3つ目は樹木や電柱。
イタチは木登りが得意。
畑の近くにある木や電柱は、イタチにとって絶好の侵入ルートなんです。
「えっ!あんな高いところから?」と驚くかもしれませんが、イタチは高所からの侵入も平気なのです。
4つ目は排水溝や配管。
イタチは細長い体を活かして、狭い場所を自在に移動します。
排水溝や配管の開口部は、イタチにとって格好の通り道。
「こんな小さな穴から入れるの?」と思うような場所でも、イタチは難なく通過してしまうんです。
最後は作物の茂み。
背の高い作物や密集した植え方は、イタチに絶好の隠れ場所を提供してしまいます。
「作物がよく育ってうれしいな」と思っていたら、それがイタチを招き入れる原因になっているかも。
これらの侵入経路を知っておくと、効果的な対策が立てられます。
例えば、フェンスの補強、地面の穴をふさぐ、木の枝払い、排水溝の網かけ、作物の間隔を広げるなど。
「よし、うちの畑の弱点はここだな」と把握できれば、イタチ対策の第一歩を踏み出せるはずです。
畑の被害放置が招く「最悪のシナリオ」に注意
イタチによる畑の被害を放置すると、想像以上に深刻な事態を招きかねません。最悪のシナリオを知ることで、早めの対策の重要性が分かるはずです。
まず、収穫量の激減です。
イタチの被害を放置すると、年々収穫量が減っていきます。
「去年はこんなにたくさん採れたのに…」という落胆の声が聞こえてきそうです。
最悪の場合、畑での作物栽培が不可能になってしまうかもしれません。
次に、経済的損失です。
収穫量が減れば、当然収入も減ります。
家計を支える大切な収入源が失われてしまうかもしれません。
「せっかく頑張って育てたのに…」という思いが募るばかりです。
さらに、家族や地域への影響も見逃せません。
新鮮な野菜を家族に提供できなくなったり、近所の人々とのおすそ分けの機会が失われたりします。
「今年は何もあげられなくてごめんね」なんて言わなければならなくなるかも。
そして、農業への情熱の喪失。
被害が続くと、畑仕事への意欲が失われていきます。
「もう畑なんてやめちゃおうかな…」なんて考えてしまうかもしれません。
長年培ってきた技術や知識が無駄になってしまうのは、本当に残念なことです。
最後に、生態系への影響。
放置された畑は、イタチだけでなく他の害獣のすみかになってしまいます。
周辺地域の生態系バランスまで崩れてしまう可能性があるのです。
イタチの被害を放置すると、こんな悲しい未来が待っているかもしれません。
でも、大丈夫。
早めの対策を取れば、こんな最悪のシナリオは避けられるはずです。
「よし、今日からイタチ対策を始めよう!」そんな前向きな気持ちで、畑を守る第一歩を踏み出しましょう。
イタチ対策で「やってはいけない」危険な方法とは
イタチ被害に困っていると、ついつい過激な対策を考えてしまいがち。でも、ちょっと待ってください!
イタチ対策には「やってはいけない」危険な方法があるんです。
まず、毒物による駆除は絶対にやめましょう。
「これで一発解決!」なんて思うかもしれませんが、大きな間違いです。
毒物は環境汚染を引き起こすだけでなく、他の生き物にも悪影響を及ぼします。
「畑のミミズさんたちが全滅しちゃった…」なんて悲しい事態になりかねません。
しかも、毒物の使用は法律で規制されているので、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も。
次に、イタチの天敵を放すのも危険です。
「イタチを追い払ってくれる動物を連れてこよう!」なんて考えるのは、ちょっと危険。
新たな生態系の問題を引き起こす可能性が高いんです。
例えば、イタチの天敵を放したら、今度はその天敵が手に負えなくなってしまうかも。
「イタチよりもっと厄介な生き物が増えちゃった…」なんて事態になりかねません。
他にも、過度な音や光による追い払いも要注意。
「うるさい音を出して追い払おう!」なんて思うかもしれませんが、周囲の迷惑になるだけでなく、他の生き物にも悪影響を与えてしまいます。
「夜中までうるさくて眠れない!」なんて苦情が来たり、畑に来る益虫まで寄り付かなくなったりする可能性も。
さらに、過剰な殺虫剤の使用も避けるべきです。
「イタチの餌になる虫を全部退治しちゃえば…」なんて考えるのは危険。
殺虫剤の過剰使用は土壌を痛め、作物の質を落としてしまいます。
「なんだか野菜の味が変…」なんて事態になりかねません。
イタチ対策は、自然のバランスを崩さない方法で行うのが大切。
「急がば回れ」ということわざがありますが、まさにその通り。
焦って危険な方法に手を出すよりも、安全で効果的な対策を地道に続けることが、長期的には最も賢明な選択なのです。
電気柵による効果的なイタチ対策の実践方法

電気柵vsフェンス!イタチ対策の決定打はどっち?
イタチ対策の決定打は間違いなく電気柵です。フェンスよりも効果的で、イタチの侵入を確実に防ぐことができます。
「え、普通のフェンスじゃダメなの?」そう思った方も多いかもしれません。
でも、イタチは驚くほど賢くて器用な動物なんです。
普通のフェンスなら、すいすいと登ってしまうんです。
電気柵とフェンス、どこが違うのでしょうか。
ここがポイントです。
- 電気柵:イタチに直接的な痛みを与えるため、強い忌避効果がある
- フェンス:物理的な障害物にはなるが、イタチは簡単に乗り越えられる
- 電気柵:一度痛い思いをすると、イタチは二度と近づかなくなる
- フェンス:イタチにとっては単なる遊び場になってしまう可能性がある
フェンスは「立入禁止」の看板のようなもの。
でも電気柵は「触ると痛いよ!」という実際の経験をさせるんです。
どっちが効果的か、分かりますよね?
「でも、電気柵って動物にかわいそうじゃない?」なんて心配する方もいるかもしれません。
大丈夫です。
電気柵の電圧は、イタチに痛みを与えるけど致命的な危害は与えないように設定されているんです。
ちょっとしたびっくり箱みたいなものですね。
ちなみに、電気柵の設置は意外と簡単。
「えっ、こんなに簡単でいいの?」って思うくらいです。
フェンスのように大掛かりな工事は必要ありません。
結局のところ、イタチ対策で大切なのは「二度と来たくない」と思わせること。
その点、電気柵は文句なしの成績優秀者なんです。
畑を守る強い味方、それが電気柵というわけです。
電気柵の設置高さと電圧設定「失敗しない3つのコツ」
電気柵の効果を最大限に引き出すには、正しい設置高さと電圧設定が決め手です。失敗しない3つのコツをお教えしましょう。
1. 適切な高さに設置する
イタチ対策の電気柵は、地上から15〜20センチメートルの高さに設置するのがベストです。
なぜこの高さなのか?
それは、イタチの平均的な体高に合わせているんです。
「えっ、そんな低くていいの?」って思うかもしれません。
でも、これがイタチの目線に合わせた絶妙な高さなんです。
イタチがぴょこんと頭を上げたときにちょうど触れる高さ、それが15〜20センチメートルなんです。
2. ワイヤーの間隔を適切に保つ
電気柵のワイヤー間隔は5〜7センチメートルが理想的。
これくらいの間隔なら、イタチがすり抜けようとしても、必ずどこかで電気に触れるんです。
「ワイヤーの間隔が広すぎると、イタチがすいすい通っちゃうかも…」そんな心配は無用です。
この間隔なら、イタチの体のどこかが必ず電気に触れるんです。
3. 適切な電圧を設定する
イタチ対策用の電気柵は、3000〜5000ボルトに設定するのが効果的です。
「うわっ、高すぎない?」って思った方、安心してください。
この電圧は、イタチに痛みを与えますが、致命的な危害は与えないんです。
イタチにとっては「びりっ」とした衝撃。
「二度と触りたくない!」と思わせるには十分な強さです。
でも、人間が誤って触れても大丈夫な範囲なんです。
これらのコツを押さえれば、電気柵の効果は抜群。
「よっしゃ、これでイタチの被害とはおさらばだ!」そんな気分になれるはずです。
電気柵、正しく使えば最強の味方になりますよ。
イタチ対策における電気柵と忌避剤の併用効果
電気柵と忌避剤を組み合わせると、イタチ対策の効果が飛躍的にアップします。これは、まるで二重のバリアを張るようなもの。
イタチを寄せ付けない強力な防御線になるんです。
まず、電気柵の役割をおさらいしましょう。
電気柵は物理的な障壁として機能し、イタチが触れると「びりっ」とした衝撃を与えます。
「二度と近づきたくない!」とイタチに思わせる強力な効果があるんです。
一方、忌避剤はどんな役割を果たすのでしょうか。
忌避剤は、イタチの嫌いな匂いを放つことで、そもそも近づかせない効果があります。
「うぇ〜、この匂い苦手〜」とイタチが思うような香りを使うんです。
では、この二つを組み合わせるとどうなるでしょうか。
- 忌避剤の匂いで遠くからイタチを寄せ付けない
- 万が一近づいてきても、電気柵で確実に撃退
- 忌避剤と電気柵の二重の記憶で、より強く畑を避けるようになる
堀(忌避剤)で敵(イタチ)の接近を防ぎ、それでも近づいてきたら城壁(電気柵)でシャットアウト。
これなら、かなり強固な防御になりますよね。
「でも、忌避剤って何を使えばいいの?」そんな疑問も出てくるはず。
実は、身近なものでも十分な効果があるんです。
例えば、ニンニクをすりつぶして畑の周りに撒くだけでもOK。
イタチは強い香りが苦手なんです。
他にも、市販の忌避剤スプレーを使うのも効果的。
電気柵の周りに定期的に吹きかけることで、より強力な防御線になります。
「よし、これで完璧!」って感じですね。
電気柵と忌避剤の併用、まさに最強のコンビネーション。
イタチ対策、これで万全です!
電気柵のメンテナンス方法と長期的な効果維持のポイント
電気柵を設置したら終わり、ではありません。長期的に効果を維持するには、適切なメンテナンスが欠かせません。
ここでは、電気柵を常に最高の状態に保つためのポイントをお教えします。
まず、定期的な点検が大切です。
電気柵は外に設置するものなので、天候や時間の経過で劣化することがあります。
月に1回くらいのペースで、次の点をチェックしましょう。
- ワイヤーの緩みや破損がないか
- 支柱がしっかり地面に固定されているか
- 電源装置が正常に作動しているか
- 周囲の草木が電気柵に触れていないか
でも、こまめなチェックが長持ちの秘訣なんです。
次に、清掃も重要です。
電気柵に草や土が付着していると、電気の流れが悪くなることがあります。
定期的に柔らかい布で拭き取りましょう。
「ちょっと面倒くさいな」と思っても、これが効果維持の決め手なんです。
電圧のチェックも忘れずに。
電圧計を使って、設定した電圧が維持されているか確認します。
「3000〜5000ボルトをキープ」、これが黄金律です。
そして、季節の変化にも注意が必要。
特に冬は、積雪で電気柵が埋もれてしまうことも。
「雪かきの時に電気柵も忘れずに!」これ、大切なポイントです。
また、周囲の環境変化にも目を配りましょう。
近くに新しい木が生えてきて、イタチの侵入経路になっていないか。
「あれ?この木、前はなかったよな」なんて気づいたら要注意です。
最後に、電池式の場合は電池の交換を忘れずに。
「あ、電池切れてた!」なんてことになったら、せっかくの電気柵も無意味になっちゃいます。
これらのポイントを押さえれば、電気柵の効果は長く続きます。
「よし、これでイタチ対策はばっちりだ!」そんな自信が持てるはずです。
定期的なケア、それが電気柵を味方につける秘訣なんです。
コスト面で比較!電気柵vs超音波装置どちらがお得?
イタチ対策、電気柵と超音波装置ではどちらがお得なのでしょうか。結論から言うと、長期的には電気柵の方がコスト効率が良いんです。
まず、初期投資を比べてみましょう。
- 電気柵:比較的高価(数万円〜)
- 超音波装置:比較的安価(数千円〜)
でも、ちょっと待ってください。
初期費用だけで判断するのは早計なんです。
長期的な運用コストを考えると、状況が変わってきます。
- 電気柵:電気代以外の維持費はほとんどかからない
- 超音波装置:電池交換が頻繁に必要、故障のリスクも高い
「あれ?また電池切れ?」なんてことが頻繁に起こりかねないんです。
耐久性の面でも電気柵に軍配が上がります。
電気柵は頑丈で長持ち。
一方、超音波装置は精密機器なので、故障のリスクが高いんです。
「せっかく買ったのに壊れちゃった…」なんて悲しい経験をする可能性が高いんです。
効果の持続性も重要なポイント。
電気柵は一度設置すれば長期間効果が続きます。
超音波装置は、イタチが慣れてしまう可能性があるんです。
「最初は効いてたのに、だんだん効かなくなってきた…」なんてことも。
さらに、電気柵は畑全体を守れるのに対し、超音波装置は効果範囲が限られます。
「あっちは守れてるけど、こっちはダメかも…」なんて心配も出てきそうです。
結局のところ、初期費用は高くても、長期的に見れば電気柵の方がお得なんです。
「先行投資は大きいけど、長い目で見ればこっちの方が賢明だな」そんな判断ができると思います。
イタチ対策、お金をかけるなら効果的なものに。
それが電気柵なんです。
「よし、これで安心して畑が守れる!」そんな安心感を手に入れられるのは、やっぱり電気柵なんです。
イタチ対策の裏技と総合的な畑の防衛戦略

古いCDで作る「イタチよけの反射板」設置方法
古いCDを使って簡単にイタチよけの反射板が作れます。この方法は手軽で効果的なイタチ対策の裏技です。
「えっ、CDでイタチが防げるの?」そう思った方も多いでしょう。
実は、CDの反射光がイタチを驚かせる効果があるんです。
イタチは急な光の変化を警戒する習性があります。
CDの反射光は、まさにイタチにとって「うわっ、何これ!」という驚きの光なんです。
では、具体的な作り方と設置方法を見ていきましょう。
- 古いCDを集める(10枚程度あれば十分)
- CDに紐を通す穴を開ける
- 紐を通してCDをつなげる
- 畑の周りの木や支柱にCDの紐を結ぶ
設置する際のポイントは、CDが風で揺れるように少し余裕を持たせることです。
風でかさかさと音を立てながら光るCDは、イタチにとって「なんだか怖いぞ」という存在になります。
また、CDの高さはイタチの目線くらいに合わせるのがコツです。
地面から15〜20センチメートルくらいの高さがちょうどいいでしょう。
「イタチの目に直接光が入るようにするんだな」と考えると、設置の高さがイメージしやすいですね。
この方法のいいところは、お金をかけずに済むことです。
「もう使わないCDがたくさんあるんだよな〜」なんて方には、ぴったりの対策方法です。
ただし、CDの反射光が近所の方の迷惑にならないよう、設置場所には気をつけましょう。
「ご近所トラブルは避けたいもんね」というわけです。
この裏技、試してみる価値ありですよ。
さあ、古いCDで畑を守りましょう!
ニンニクとハーブの力でイタチを寄せ付けない「香りの壁」
ニンニクとハーブを使って、イタチを寄せ付けない「香りの壁」を作ることができます。この方法は自然な材料で畑を守れる、エコで効果的な裏技です。
イタチは鋭敏な嗅覚を持っています。
そのため、強い香りを嫌う傾向があるんです。
「イタチさんにとっては、香りが強すぎてくしゃみが出そう!」というイメージでしょうか。
では、具体的な方法を見ていきましょう。
- ニンニク水の作り方
- ニンニクを5〜6片つぶす
- 1リットルの水に浸す
- 一晩置いて成分を抽出
- 効果的なハーブの種類
- ミント
- ローズマリー
- ラベンダー
- 設置方法
- 畑の周りにニンニク水を散布
- ハーブを鉢植えで配置
でも、これが意外と効果があるんです。
ニンニク水は週に1〜2回程度散布するのがおすすめです。
「畑がニンニク臭くなっちゃうんじゃ...」なんて心配する必要はありません。
人間には気にならない程度の薄さで十分効果があります。
ハーブは生きた植物なので、継続的に香りを放ち続けます。
しかも、畑の景観も良くなるという一石二鳥の効果も。
「うちの畑、なんだかお洒落になったぞ」なんて喜びも味わえるかもしれません。
この方法のいいところは、化学物質を使わないので安心安全なことです。
「食べる野菜を育てる畑だから、なるべく自然なもので守りたいよね」という方にぴったりです。
ただし、効果を持続させるには定期的なメンテナンスが必要です。
ニンニク水の散布を忘れずに、ハーブの手入れもこまめにしましょう。
「ちょっと手間はかかるけど、それだけの価値はある!」と思えるはずです。
さあ、香りの力で畑を守りましょう。
イタチさんにとっては「立入禁止ゾーン」の出来上がりです!
ペットボトルを利用した「イタチ撃退ライトトラップ」の作り方
ペットボトルを使って、イタチを撃退する光のトラップが作れます。この方法は、身近な材料で作れる上に、見た目もユニークで効果的な裏技です。
イタチは予期せぬ光の変化を警戒します。
ペットボトルの中の水が光を屈折させ、キラキラと不規則に光る様子は、イタチにとって「うわっ、なんだこれ!」という驚きの的なんです。
では、具体的な作り方を見ていきましょう。
- 材料準備
- 透明なペットボトル(1.5〜2リットル)
- 水
- 小さな鏡やアルミホイル
- 紐
- 作り方
- ペットボトルの上部を切り取る
- ボトルに水を8分目まで入れる
- 小さな鏡やアルミホイルを水面に浮かべる
- 切り取った上部を逆さまに差し込む
- 紐を取り付ける
- 設置方法
- 畑の周りの木や支柱に吊るす
- 地面から20〜30センチの高さに設置
でも、これが意外と効くんです。
ポイントは、ペットボトルが風で少し揺れるように設置すること。
風で揺れると、中の水面が波打ち、光の反射がより不規則になります。
「まるで小さなディスコボールみたい!」なんて感じですね。
この方法のいいところは、昼も夜も効果を発揮すること。
昼間は太陽光を、夜は月光や街灯の光を利用します。
「24時間体制でイタチ対策、すごい!」って感じですよね。
ただし、定期的に水を入れ替えるのを忘れずに。
「緑色の水になっちゃった...」なんてことにならないよう、週に1回程度の水替えがおすすめです。
また、強風で飛ばされないよう、しっかり固定することも大切です。
「台風の後に畑中ペットボトルだらけ」なんて悲劇は避けたいですものね。
この裏技、ちょっと変わってるけど効果的。
さあ、ペットボトルでイタチ撃退、始めてみましょう!
畑の周りに砂を敷く「足跡トラップ」でイタチの侵入を防止
畑の周りに砂を敷いて「足跡トラップ」を作る方法は、イタチの侵入を防ぐ効果的な裏技です。この方法は、イタチの習性を利用した賢い対策なんです。
イタチは足跡を残すのを嫌がる習性があります。
「自分の行動が追跡されるのは危険!」とイタチは考えるんです。
砂の上を歩けば必ず足跡が残るため、イタチは砂の上を歩くのを避けようとします。
では、具体的な作り方と効果を見ていきましょう。
- 材料準備
- 細かい砂(海砂や川砂がおすすめ)
- シャベルや熊手
- 設置方法
- 畑の周囲に幅30〜50センチの帯状に砂を敷く
- 砂の厚さは3〜5センチ程度
- 表面をきれいに平らにならす
- 効果の確認方法
- 毎朝、砂の上に足跡がないか確認
- 足跡があれば、イタチの侵入経路が分かる
でも、これが意外と効果的なんです。
この方法のポイントは、砂の幅をしっかり確保することです。
幅が狭いと、イタチが飛び越えてしまう可能性があります。
「よーいどん!でジャンプ」なんて感じでね。
幅を広くすれば、イタチも「うーん、ちょっと遠いなぁ」と躊躇するわけです。
さらに、この方法には別の利点もあります。
もしイタチが侵入しても、足跡が残るので侵入経路が分かるんです。
「あ、ここから入ってきたんだな」と特定できれば、そこを重点的に対策できます。
ただし、雨が降ったり風が強かったりすると、砂がならされてしまいます。
「せっかく敷いた砂が台無し...」なんてことにならないよう、定期的にメンテナンスするのを忘れずに。
また、野菜の近くに砂を敷くと、野菜に砂がかかってしまう可能性があります。
「せっかくの野菜が砂まみれ」なんて悲しいことにならないよう、適切な距離を保つことが大切です。
この裏技、ちょっと地味かもしれませんが、効果は抜群。
さあ、砂の力でイタチの侵入を防ぎましょう!
風車とアルミホイルで作る「動く音と光のイタチよけ」
風車とアルミホイルを組み合わせた「動く音と光のイタチよけ」は、イタチを寄せ付けない効果的な裏技です。この方法は、イタチの視覚と聴覚の両方に働きかける、まさに一石二鳥の対策なんです。
イタチは予期せぬ動きや音を警戒します。
風車の回転する動きと、それに伴う音、さらにアルミホイルの反射光が組み合わさると、イタチにとっては「うわっ、なんだか怖い!」という存在になるんです。
では、具体的な作り方と設置方法を見ていきましょう。
- 材料準備
- 小型の風車(100円ショップで購入可能)
- アルミホイル
- 紐
- ハサミ
- 作り方
- 風車の羽根にアルミホイルを巻き付ける
- 風車の軸に紐を結ぶ
- 設置方法
- 畑の周りの木や支柱に吊るす
- 地面から30〜50センチの高さに設置
- 複数個所に設置するとより効果的
でも、これがなかなか侮れないんです。
ポイントは、風車が自由に回転できるように設置すること。
風が吹くたびにくるくる回り、カラカラ音を立て、キラキラ光る...これはイタチにとって「なんだか落ち着かないぞ」という空間になります。
この方法のいいところは、風の力を利用するので電気代がかからないこと。
「エコで経済的、いいじゃない!」って感じですよね。
また、見た目もなかなかユニークで、畑に楽しい雰囲気をもたらすこと。
「畑が風車だらけになっちゃった!」なんて笑える光景になるかもしれません。
ただし、強風時には風車が飛ばされないよう、しっかり固定することが大切です。
「台風の後に風車が近所中に散らばってた...」なんて悲劇は避けたいですよね。
また、アルミホイルは定期的に交換するのがおすすめです。
「くしゃくしゃになってちっとも光らなくなっちゃった」なんてことにならないよう、月に1回程度の点検と交換を心がけましょう。
この裏技、ちょっと面白くて効果的。
さあ、風車とアルミホイルでイタチを撃退、始めてみましょう!
「よし、これで我が畑は風車村だ!」なんて気分で楽しみながら対策できるはずです。