イタチを効果的に避ける環境整備法【餌場と隠れ家をなくす】再侵入を防ぐ5つの長期的対策

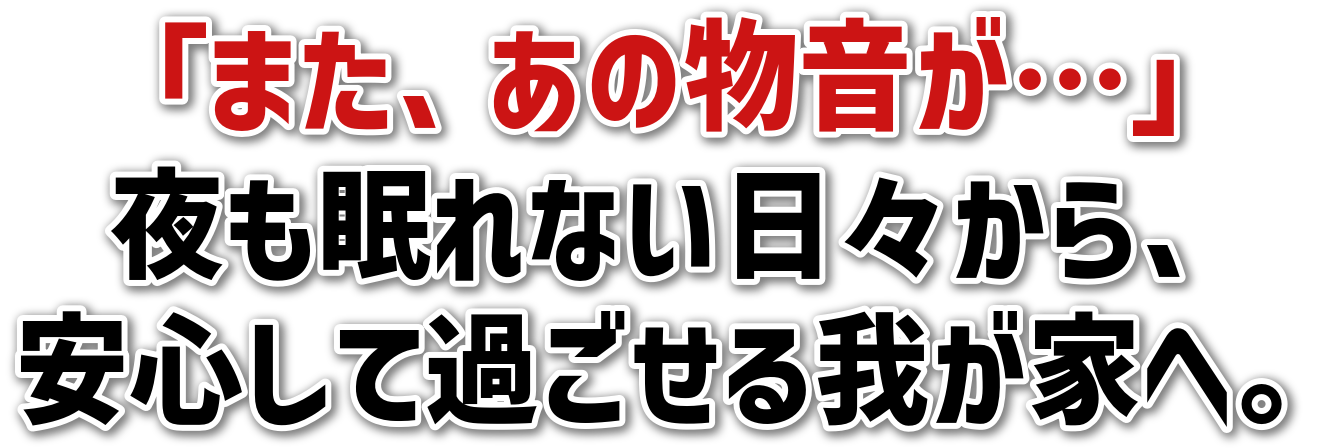
【この記事に書かれてあること】
イタチの被害に悩まされていませんか?- イタチが好む「餌と隠れ家」を理解し除去
- 5mm以上の隙間をふさぎ侵入経路を遮断
- 物理的障壁と化学的忌避剤の使い分け
- 自然な方法と人工的な方法の長期的効果を比較
- 音と光を活用したイタチ撃退の裏技
実は、効果的な環境整備でイタチを寄せ付けない家を作ることができるんです。
この記事では、イタチが好む「餌場」と「隠れ家」をなくす5つの驚きの裏技をご紹介します。
「ガサガサ」「ゴソゴソ」という不気味な物音とはさようなら。
身近な材料を使った簡単な対策で、イタチフリーな快適空間を手に入れましょう。
あなたの家族や大切な家を守るための、具体的で実践的な方法をお伝えします。
さあ、イタチとの「いたちごっこ」から卒業する時です!
【もくじ】
イタチが好む環境と侵入経路を知り対策の第一歩へ

イタチの習性を理解!「餌と隠れ家」が重要ポイント
イタチを寄せ付けない環境づくりの第一歩は、その習性を知ることです。イタチが大好きなのは、「餌が豊富」で「隠れ家がたくさんある」場所なんです。
「えっ、そんな単純なの?」と思われるかもしれません。
でも、この2つを押さえるだけで、イタチ対策はぐっと効果的になるんです。
まず、イタチの大好物について見てみましょう。
- ネズミ
- 小鳥
- 昆虫
- カエル
「ここなら腹いっぱい食べられるぞ!」とばかりに、どんどん寄ってきちゃうんです。
次に、イタチが喜ぶ隠れ家をチェック!
- 生い茂った薮
- 積み重ねた木材
- 放置された古い家具
- 建物の隙間
「ここなら安心して休めるし、子育てもできるぞ!」なんて考えているかもしれません。
つまり、イタチ対策の基本は「餌を減らす」+「隠れ家をなくす」。
この2つを押さえれば、イタチに「ここは住みにくいぞ」と思わせることができるんです。
ガサガサ、ゴソゴソと物音がしなくなる日も、そう遠くないかもしれません。
庭や家の周りの整理整頓が「最初の一手」だ!
イタチ対策の第一歩は、意外にも身近なところにあります。それは、庭や家の周りの整理整頓なんです。
「えっ、そんな簡単なこと?」と思われるかもしれません。
でも、これが実は大きな効果を発揮するんです。
まず、庭の状態をチェックしてみましょう。
- 伸び放題の草木
- 積み上げられた木材や資材
- 放置された古い道具や家具
- ゴミの山
「ここなら安心して暮らせるぞ!」とイタチは喜んでいるかもしれません。
では、具体的にどう整理整頓すればいいのでしょうか?
1. 草刈りをしっかり行う
長く伸びた草は、イタチの絶好の隠れ場所。
定期的に刈り込んで、見通しをよくしましょう。
2. 不要な物は処分する
「いつか使うかも」と思って置いてある物も、イタチの住処になりかねません。
思い切って処分しましょう。
3. 資材はきちんと整理して保管
どうしても置いておく必要がある場合は、イタチが入り込めないように、しっかりと整理して保管しましょう。
4. ゴミは適切に管理
生ゴミはイタチの大好物。
密閉容器に入れるなど、適切に管理することが大切です。
こうして整理整頓を行うと、イタチにとって「ここは住みにくいぞ」という環境が整います。
「ガサガサ」「ゴソゴソ」という不気味な物音も、徐々に聞こえなくなっていくはずです。
さあ、今日からさっそく始めてみましょう。
きっと、イタチフリーな快適空間が待っていますよ。
イタチの主食「小動物」を寄せ付けない環境作り
イタチ対策の要は、その主食となる小動物を寄せ付けないこと。これさえ押さえれば、イタチの来訪を大幅に減らせるんです。
「え、そんな簡単なの?」と思われるかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
まず、イタチの大好物リストをチェックしてみましょう。
- ネズミ
- 小鳥
- 昆虫
- カエル
では、具体的にどうすれば小動物を寄せ付けない環境が作れるのでしょうか?
1. ゴミの適切な管理
生ゴミはネズミや昆虫の大好物。
密閉容器に入れるなど、しっかり管理しましょう。
「ゴミ出しはルールを守って」が合言葉です。
2. 鳥の餌やりは控えめに
「かわいい小鳥たちに餌をあげたい」という気持ちはわかります。
でも、それがイタチを呼び寄せる原因に。
餌やりは控えめにしましょう。
3. 昆虫を寄せ付けない照明の使用
虫が寄ってくる明るい照明は避け、虫が苦手な黄色や赤色の光を使うのがおすすめ。
「ブーン」という虫の羽音も減りますよ。
4. 水たまりをなくす
カエルやボウフラの発生源になる水たまりは要注意。
庭に水がたまりやすい場所があれば、早めに対処しましょう。
5. 草刈りを定期的に
背の高い草はネズミや昆虫の絶好の隠れ家に。
「ザクザク」と定期的に刈り込んで、すっきりした環境を保ちましょう。
このように小動物を寄せ付けない環境を整えることで、イタチにとっては「ここには美味しい食べ物がないぞ」というメッセージを送ることができるんです。
頑張って対策を続けていると、ある日「あれ?最近イタチ見てないな」と気づく日が来るかもしれません。
そんな日を目指して、一緒に頑張りましょう!
イタチの侵入口となる「5mm以上の隙間」をチェック!
イタチ対策で見落としがちなのが、建物の隙間。なんと、5mm以上の隙間があれば、イタチは簡単に侵入できてしまうんです。
「えっ、そんな小さな隙間から?」と驚かれるかもしれません。
でも、これが事実なんです。
まず、イタチが侵入しやすい場所をチェックしてみましょう。
- 屋根裏の換気口
- 壁の隙間
- 床下の通気口
- 配管やケーブルの周り
- 戸袋や窓枠の隙間
では、具体的にどうやってチェックし、対策すればいいのでしょうか?
1. 目視での確認
まずは、家の外周りをじっくり観察します。
「あれ?ここに隙間が...」と気づくことも多いはずです。
2. 煙を使ったチェック
煙の出る線香を使うと、小さな隙間も見つけやすくなります。
「スーッ」と煙が漏れる場所が要注意です。
3. 光を使った確認
夜に家の中から強い光を当てて、外から隙間を探すのも効果的。
「ポッ」と光が漏れる場所がイタチの侵入口かもしれません。
4. 専用の道具を使う
5mmのゲージや物差しを使って、隙間の大きさを実際に測ってみましょう。
「ほんの少しだけど、5mmはあるな...」という場所が要チェックです。
5. 定期的なメンテナンス
建物は年月とともに劣化します。
定期的なチェックと補修が大切です。
「去年は大丈夫だった」と油断は禁物です。
隙間が見つかったら、すぐに対策を。
金属製のメッシュや専用のシール材で塞ぐのが効果的です。
「よし、これでイタチは入れないぞ!」と思えるまで、しっかり対策しましょう。
こうして隙間を塞いでいくと、イタチにとっては「ここには入れる場所がないぞ」という難攻不落の要塞ができあがります。
ガサガサ、ゴソゴソという不気味な物音とはさようなら。
快適な生活が待っていますよ。
イタチを寄せ付けない効果的な対策と比較

物理的な障壁vs化学的な忌避剤!長期的効果は?
イタチ対策には、物理的な障壁と化学的な忌避剤の2つの方法がありますが、長期的には物理的な障壁の方が効果的です。「えっ、そうなの?」と思われるかもしれません。
確かに、化学的な忌避剤は手軽で即効性がありますよね。
でも、長い目で見ると物理的な障壁の方が優れているんです。
まず、物理的な障壁の特徴を見てみましょう。
- イタチの侵入を物理的に防ぐ
- 一度設置すれば長期間効果が持続
- 環境にやさしい
- メンテナンスが比較的簡単
「ここから先には入れないぞ!」とイタチに明確なメッセージを送れるんです。
一方、化学的な忌避剤はどうでしょうか。
- イタチを嫌がらせて近づかせない
- 定期的な再塗布や散布が必要
- 環境への影響が心配
- イタチが慣れてしまう可能性がある
でも、その効果は一時的。
雨で流されたり、時間とともに薄れたりしてしまいます。
長期的に見ると、物理的な障壁は一度設置すれば何年も効果が続きます。
「ガッチリ守られてる!」という安心感も得られますよね。
化学的な忌避剤は効果を維持するために頻繁な手入れが必要で、「また塗らなきゃ...」とちょっと面倒くさくなっちゃうかもしれません。
もちろん、状況によっては両方を組み合わせるのも良い選択肢です。
物理的な障壁で大まかに防ぎつつ、侵入されやすい場所に忌避剤を使うという具合に。
これで、イタチに「ここは絶対ダメだぞ」とダブルで伝えられるんです。
自然な方法vs人工的な方法!生態系への影響は?
イタチ対策において、自然な方法と人工的な方法を比較すると、生態系への影響を考慮すれば自然な方法の方が優れています。「え?自然な方法って効果あるの?」と思われるかもしれません。
でも、実は自然な方法には思わぬ威力があるんです。
まず、自然な方法の特徴を見てみましょう。
- 生態系を乱さない
- 人や他の動物への悪影響が少ない
- 長期的に持続可能
- コストが比較的安い
「ここは居心地悪いな」とイタチに思わせることができるんです。
一方、人工的な方法はどうでしょうか。
- 即効性がある
- 効果が目に見えやすい
- 生態系に影響を与える可能性がある
- 長期的には高コストになることも
確かに効果は早いですが、他の生き物にも影響を与えかねません。
自然な方法の具体例を挙げてみましょう。
- ミントやラベンダーなど、イタチが嫌う香りの植物を植える
- 天敵の尿(例:キツネやオオカミ)の匂いを利用する
- 庭を整備し、イタチの隠れ場所をなくす
- 自然素材の忌避剤(例:唐辛子スプレー)を使用する
「ふんわり」とした対策ですが、長期的には効果的なんです。
人工的な方法も時と場合によっては必要かもしれません。
でも、できるだけ自然な方法を試してみることをおすすめします。
「自然と調和しながらイタチ対策」、素敵じゃないですか?
即効性のある対策vs長期的な対策!優先すべきは?
イタチ対策を考える上で、即効性のある対策と長期的な対策、どちらを優先すべきでしょうか?結論から言うと、長期的な対策を基本としつつ、必要に応じて即効性のある対策を組み合わせるのが最適です。
「えっ、両方やるの?」と思われるかもしれません。
でも、これが実は一番効果的なんです。
まず、即効性のある対策の特徴を見てみましょう。
- すぐに効果が現れる
- 緊急時に有効
- 一時的な解決策になる
- 繰り返し行う必要がある場合も
緊急事態には確かに効果的ですよね。
一方、長期的な対策はどうでしょうか。
- 効果が現れるまで時間がかかる
- 持続的な解決策になる
- 根本的な問題に対処できる
- 一度整備すれば効果が長く続く
じわじわと、でも確実に効果を発揮します。
では、具体的にどう組み合わせればいいのでしょうか?
例えば、庭にイタチが頻繁に現れる状況を想像してみましょう。
1. まず、即効性のある対策として、市販の忌避剤を使用します。
「シュッシュッ」とスプレーするだけで、とりあえずイタチを遠ざけられます。
2. 同時に、長期的な対策として庭の整備を始めます。
草刈りをしたり、不要な物を片付けたりして、イタチの隠れ場所をなくしていきます。
3. さらに、イタチの好まない植物を植えるなど、自然な防御策も徐々に整えていきます。
このように、即効性のある対策で当面の問題に対処しつつ、長期的な対策でじっくりと環境を改善していくのが理想的です。
「今すぐどうにかしたい!」という気持ちはわかりますが、同時に「これからずっと平和に暮らしたい」という願いも大切にしましょう。
両方のアプローチを上手く組み合わせることで、イタチとの「いたちごっこ」から卒業できるはずです。
がんばりましょう!
音による対策vs光による対策!夜間の効果は?
イタチ対策において、音による方法と光による方法、どちらが夜間により効果的でしょうか?実は、両方とも効果があるんです。
でも、使い方次第で効果に差が出てきます。
「え?音と光ってそんなに違うの?」と思われるかもしれません。
でも、イタチにとっては大きな違いなんです。
まず、音による対策の特徴を見てみましょう。
- イタチの聴覚に直接働きかける
- 広い範囲に効果がある
- 人間にも聞こえる可能性がある
- イタチが慣れる可能性もある
特に、超音波装置は効果的です。
一方、光による対策はどうでしょうか。
- イタチの行動を制限する
- 局所的な効果がある
- 人間の生活にも影響する可能性がある
- 電気代がかかる
夜行性のイタチにとって、明るい場所は不快なんです。
では、夜間の効果を比較してみましょう。
音による対策:
- 24時間継続して使用可能
- 周囲の住民に迷惑をかける可能性がある
- イタチが音に慣れてしまう可能性がある
- 夜間のみの使用で効果的
- 他の夜行性動物にも影響を与える
- 人間の睡眠を妨げる可能性がある
例えば、庭に動体感知式のライトを設置し、同時に超音波装置も使用する。
イタチが近づくと「ピカッ」と光が点き、「キーン」という音も鳴る。
これなら、イタチに「うわっ、ここは危険だ!」と強烈に印象づけられますよね。
ただし、近所迷惑にならないよう注意が必要です。
「ガンガン」とうるさい音を出したり、「ギラギラ」と眩しい光を照らしたりするのは避けましょう。
結局のところ、状況に応じて使い分けるのが賢明です。
静かな住宅街なら光を、音が気にならない場所なら音を。
そして可能なら両方を。
これで、イタチに「ここは居心地が悪いぞ」とダブルで伝えられるんです。
庭の整備vs建物の補強!コストパフォーマンスは?
イタチ対策として、庭の整備と建物の補強、どちらがコストパフォーマンスに優れているでしょうか?結論から言うと、まずは庭の整備から始めるのがおすすめです。
「えっ、建物を補強しなくていいの?」と思われるかもしれません。
でも、実は庭の整備の方が手軽で効果的なんです。
まず、庭の整備のメリットを見てみましょう。
- 比較的低コストで実施可能
- 自分でもできる部分が多い
- イタチの隠れ場所や餌場を一気に減らせる
- 庭全体の美観も向上する
「ここは住みにくいぞ」とイタチに伝えられるんです。
一方、建物の補強はどうでしょうか。
- 確実にイタチの侵入を防げる
- 専門知識や技術が必要なことも
- コストが高くなりがち
- 一度やれば長期的な効果が期待できる
確かに効果は高いですが、お財布にはちょっと厳しいかも。
では、具体的な行動とコストを比較してみましょう。
庭の整備:
- 草刈り:自分でやれば無料、業者依頼で5000円ほど
- 不要物の撤去:無料(自己処分の場合)
- イタチの嫌う植物の植栽:苗1本500円ほどから
- フェンスの設置:1mあたり5000円ほどから
- 屋根裏への侵入口封鎖:数万円から
- 外壁の隙間補修:1箇所あたり1万円ほどから
- 換気口への防護ネット設置:1箇所5000円ほどから
- 床下への侵入防止:数万円から
「えっ、こんなに違うの?」と驚かれるかもしれません。
さらに、庭の整備には副次的な効果もあります。
例えば、庭がきれいになることで家の価値が上がったり、虫や他の害獣も寄り付きにくくなったりするんです。
まさに一石二鳥、いや一石三鳥くらいの効果があるかも!
ただし、イタチが既に建物に侵入している場合は話が変わってきます。
その時は建物の補強も必要になるでしょう。
でも、まずは庭の整備から始めて、様子を見るのがコストパフォーマンス的には賢明です。
「よし、まずは庭から手をつけよう!」そんな気持ちになりませんか?
庭いじりを楽しみながら、イタチ対策もできる。
素敵なアイデアだと思いませんか?
さあ、早速始めてみましょう!
イタチ対策の驚きの裏技と長期的な環境整備

古い靴下で作る「ミントオイル忌避剤」の威力!
イタチ撃退の裏技として、古い靴下とミントオイルを使った忌避剤が驚くほど効果的です。「えっ、靴下?ミント?」と思われるかもしれません。
でも、これが意外と強力なイタチ対策になるんです。
まず、準備するものは簡単です。
- 使わなくなった靴下
- ミントオイル(100円ショップでも手に入ります)
- 小さな容器
靴下にミントオイルを数滴たらし、小さく丸めるだけ。
「これで本当に効くの?」と半信半疑かもしれませんが、実はイタチは強い香りが大の苦手なんです。
さて、この「ミント靴下」をどこに置けばいいでしょうか?
- イタチの侵入経路と思われる場所
- 家の周りの隅っこ
- 庭の木の下や茂みの中
- 屋根裏や床下の入り口付近
ただし、注意点もあります。
強すぎる香りは人間にも不快かもしれません。
「家中がミント臭くなっちゃった!」なんてことにならないよう、使用量は控えめにしましょう。
また、効果を維持するためには、2週間に1回程度、ミントオイルを足す必要があります。
「シュッシュッ」と霧吹きで吹きかけるのも良いでしょう。
この方法のいいところは、安価で環境にやさしいこと。
化学薬品を使わないので、お子さんやペットがいる家庭でも安心して使えます。
さあ、早速試してみましょう。
あなたの古い靴下が、イタチ撃退の強力な味方に変身するかもしれませんよ!
使用済み猫砂で演出!「天敵の存在」を匂いで伝える
イタチを寄せ付けない意外な方法として、使用済みの猫砂を活用する裏技があります。これは、イタチの天敵である猫の存在を匂いで演出するという驚きの作戦です。
「えっ、使用済みの猫砂?汚いんじゃ...」と思われるかもしれません。
でも、これが実はイタチにとっては強力な警告信号になるんです。
まず、この方法のポイントを見てみましょう。
- イタチは猫を天敵と認識している
- 動物は匂いで周囲の状況を判断する
- 猫の尿の匂いは「危険」のサインになる
- 使用済み猫砂には猫の尿の成分が含まれている
1. 猫を飼っている友人や知人から使用済みの猫砂をもらう
2. 小さな布袋や網袋に入れる
3. イタチの侵入経路や活動範囲と思われる場所に置く
「ポイポイ」と庭に撒くのではなく、袋に入れて置くことがコツです。
これで見た目も清潔に保てます。
効果的な配置場所は以下の通りです。
- 庭の隅や茂みの中
- 家の周りの植え込み
- 屋根裏や床下の入り口付近
- イタチの足跡が見つかった場所
また、化学物質を使わないので環境にも優しいんです。
ただし、注意点もあります。
強い匂いが苦手な方もいるでしょうし、近所の猫が寄ってくる可能性もあります。
「うちの庭が猫の集会所になっちゃった!」なんてことにならないよう、使用量や場所には気をつけましょう。
また、雨で流されたり、時間とともに効果が薄れたりするので、1〜2週間おきに交換するのがおすすめです。
この意外な方法で、イタチに「ここは猫のテリトリーだ!」というメッセージを送ってみませんか?
きっと、イタチも「ここは危険だぞ」と感じて寄り付かなくなるはずです。
風車と風鈴の不規則な音!イタチを警戒させる効果
イタチ対策の意外な裏技として、風車と風鈴を活用する方法があります。これらが生み出す不規則な音や動きが、イタチを警戒させる効果があるんです。
「え?そんな簡単なもので効果があるの?」と思われるかもしれません。
でも、実はイタチは予測できない音や動きに対してとても敏感なんです。
まず、この方法のポイントを見てみましょう。
- イタチは突然の音や動きに警戒心を抱く
- 風車の回転する姿は視覚的な威嚇になる
- 風鈴の音は聴覚に訴える効果がある
- 風の強さで変化する不規則さがポイント
1. 庭や家の周りの複数箇所に風車を立てる
2. 軒下や木の枝に風鈴をぶら下げる
3. 大小さまざまな風車や風鈴を組み合わせる
「カラカラ」「チリンチリン」という風鈴の音、「クルクル」と回る風車の動き。
これらが不規則に組み合わさることで、イタチに「ここは危険かもしれない」と感じさせるんです。
効果的な配置場所を挙げてみましょう。
- 庭の入り口付近
- イタチの通り道と思われる場所
- 家の周りの植え込みの中
- 屋根や軒下の近く
- フェンスや塀の上
お庭の雰囲気も良くなりますし、子どもたちも喜ぶかもしれませんね。
ただし、注意点もあります。
近所迷惑にならないよう、風鈴の音量には気をつけましょう。
また、台風など強風の際は一時的に撤去するなど、安全面にも配慮が必要です。
「よし、我が家の庭を不思議な音の庭園にしよう!」そんな気分で始めてみませんか?
イタチ対策をしながら、素敵な庭づくりができるかもしれません。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるかも!
夜間のLED照明作戦!イタチの行動を制限する方法
イタチ対策の効果的な方法として、夜間のLED照明作戦があります。これは、イタチの夜行性という特性を利用して、その行動を制限する巧妙な方法なんです。
「え?ただ明るくするだけ?」と思われるかもしれません。
でも、これが意外と強力なイタチ対策になるんです。
まず、この方法のポイントを押さえましょう。
- イタチは主に夜間に活動する
- 暗闇を好み、明るい場所を避ける傾向がある
- 突然の光に警戒心を抱く
- LED照明は省エネで長時間使用可能
1. 庭や家の周りの暗い場所にLED照明を設置する
2. 人感センサー付きの照明を使用する
3. タイマー式の照明で時間帯を設定する
「ピカッ」と突然光るセンサーライトは、イタチにとってはとてもビックリする存在なんです。
「うわっ、何か来た!」と思って逃げ出してしまうわけです。
効果的な設置場所を見てみましょう。
- 庭の入り口や通路
- 家の周りの暗がり
- イタチの足跡が見つかった場所
- 木々の根元や茂みの近く
- 屋根裏や床下の入り口付近
イタチだけでなく、不審者対策にもなるので一石二鳥です。
ただし、注意点もあります。
近隣の迷惑にならないよう、光の方向や強さには気をつけましょう。
また、他の夜行性動物や昆虫にも影響を与える可能性があるので、使用時間や場所は適切に設定する必要があります。
「我が家の夜の庭が、まるでイルミネーションみたい!」なんて楽しみ方もできるかもしれません。
イタチ対策をしながら、素敵な夜の庭を演出できるなんて素敵じゃありませんか?
さあ、あなたも夜の庭を明るく照らして、イタチに「ここは危険だぞ」とアピールしてみましょう。
きっと、イタチも「ちょっと、ここは居心地が悪いな」と感じるはずです。
コーヒーかすの驚きの効果!強い臭いで撃退する秘策
イタチ対策の意外な裏技として、コーヒーかすを活用する方法があります。この身近な廃棄物が、実はイタチを寄せ付けない強力な武器になるんです。
「えっ、コーヒーかす?」と驚かれるかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
まず、この方法のポイントを確認しましょう。
- イタチは強い匂いが苦手
- コーヒーの香りは人間には心地よいが、イタチには刺激的
- 湿気を吸う性質があり、カビの発生も抑える
- 無料で手に入る上、環境にも優しい
1. 使用済みのコーヒーかすを天日干しで乾燥させる
2. 小さな布袋や網袋に入れる
3. イタチの侵入経路や活動範囲に配置する
「サラサラ」と乾いたコーヒーかすを使うのがポイントです。
湿ったままだとカビの原因になってしまいますからね。
効果的な配置場所は以下の通りです。
- 庭の隅や植え込みの中
- 家の周りの地面
- イタチの足跡が見つかった場所
- 屋根裏や床下の入り口付近
- ゴミ置き場の周辺
コーヒーを飲む習慣がある家庭なら、毎日新鮮なコーヒーかすが手に入りますよね。
ただし、注意点もあります。
雨で流されたり、時間とともに効果が薄れたりするので、1週間おきくらいに交換するのがおすすめです。
また、ペットが食べてしまう可能性もあるので、直接地面にまくのではなく、袋に入れて置くのが安全です。
「我が家の庭が、まるでカフェのよう!」なんて楽しい想像もできますね。
イタチ対策をしながら、良い香りの庭づくりができるなんて素敵じゃありませんか?
さあ、あなたも毎日のコーヒータイムを、イタチ撃退タイムに変えてみませんか?
きっと、イタチも「ここは居心地が悪いぞ」と感じて寄り付かなくなるはずです。
コーヒーの香りで、平和な日々を取り戻しましょう。
この身近な材料を使ったイタチ対策、意外と効果的かもしれません。
毎日のコーヒータイムが、イタチとの平和な共存につながるなんて、素敵な循環ですね。
さあ、今日からコーヒーかすを捨てずに取っておいてみましょう。
きっと、新しい発見があるはずです。